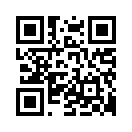2013年12月08日
第二回目 植生調査&落ち葉掻き&廃材移動
12月7日(土) 里山部会の活動
恐縮ではあるが、大学生のこういった活動に興味をお持ちの方には是非読んでいただきたい。
私(小林)のこだわりにより、俗な(一般的に行われている形の)活動をしていても面白くないので、出来る限り、体力の持つ限り色々と試行錯誤工夫をこらした活動内容を盛り込んでいきたいと思う。
ただ、一般的な里山活動を好まないといって、日本の里山の急激な変遷期にある「いま」をしっかり理解し、本質を捉えた活動を行うという基本的な路線からは離れてはいけないと思っている。
今回の活動理念、それは「安全第一に楽しく無理せず行うこと」とした。
① 活動スケジュール
11時〜12時半:植生調査(汚れてもいい服装、靴、軍手、記録に要する物(ボード、記録用紙、ペンを各2セット)、カメラ
12時半〜13時:昼休憩(山の中で手持ちのご飯をいただく。)
13時〜13時半:倒れた材を運び出し(ノコギリ、軍手)
13時半〜14時:落ち葉掻き(軍手、ビニール袋2枚)
① 活動内容
以下に行った3つの活動内容に関して詳細に記述する。
「目的」「方法」「成果」「課題」の4項目に関して記述している。
☆ 植生調査:
目的は、現状を知り記録として残すことだった。
記録として残す際に必要な項目については、エリア内の植生の現状把握という目的に従い、「樹種」とその「分布」とした。
この2項目を地図(手書き)に書き入れ、その際樹種は記号に直して表示した。エリアを東西に2分し、分担して各2名ずつが担当し、小林は両班のサポート(樹種の同定係)として調査を行った。
見られた樹種:コナラ、ソヨゴ、ネジキ、コバノミツバツツジ、モチツツジ、ヤマザクラ、カナメモチ、モウソウチク、ハチク、タカノツメ、フジ、ヒサカキ、アラカシ、シダ類、ヒイラギ
※気がついたことは欄外に書いた。(例:株立ちしている、枯れている、萌芽している、ナラ枯れ被害あり)
成果:
⑴5人で行った分、逆に個々人が躍動してくれ、思った以上に樹種に興味を持って取り組めたこと。
⑵調査を通して樹種の傾向が感覚的に捉えられたこと。
課題:
⑴斜面の情報をデータとして入れることが出来なかったこと。(天候条件が大きく異なるから。)
⑵エリア総面積を測るのを忘れていたこと。
☆廃材(言い方が気に食わないが。)の移動
目的は今後安全に活動をするための足場を作る為だった。運び出した材の利用法は検討すべきであると感じた。
活動エリア中央と東にの2カ所に溜めた。
成果:
⑴活動の足場の確保はできたこと。
課題:
⑴利用法について検討・議論の余地が大いにあるということ。
Ex.チップ化して土壌改良剤、透水性遊道、芝育成、竹炭、バンブーティー、農園芸マルチ材、堆肥化して法面緑化、ツルで束ねて荷物置き・ベンチ化etc
☆ 落ち葉掻き:
目的は林床に光を与えること、また堆肥作り。設置場所は倉庫側か山の入り口。設置容器作り。(宇佐美:担当)
次回の会議時に発表してもらう。
成果:
⑴行えたこと自体に意味があった。
課題:
⑴会議で話し合って行く予定。
以上です。
なかなか皆さんの予定が合わずに大勢の参加とはなりませんが、今後も楽しく安全にやっていきましょう!
活動日時:12月7日
活動時間:11時〜14時
活動メンバー:5人(全て2回生)
文責:小林
恐縮ではあるが、大学生のこういった活動に興味をお持ちの方には是非読んでいただきたい。
私(小林)のこだわりにより、俗な(一般的に行われている形の)活動をしていても面白くないので、出来る限り、体力の持つ限り色々と試行錯誤工夫をこらした活動内容を盛り込んでいきたいと思う。
ただ、一般的な里山活動を好まないといって、日本の里山の急激な変遷期にある「いま」をしっかり理解し、本質を捉えた活動を行うという基本的な路線からは離れてはいけないと思っている。
今回の活動理念、それは「安全第一に楽しく無理せず行うこと」とした。
① 活動スケジュール
11時〜12時半:植生調査(汚れてもいい服装、靴、軍手、記録に要する物(ボード、記録用紙、ペンを各2セット)、カメラ
12時半〜13時:昼休憩(山の中で手持ちのご飯をいただく。)
13時〜13時半:倒れた材を運び出し(ノコギリ、軍手)
13時半〜14時:落ち葉掻き(軍手、ビニール袋2枚)
① 活動内容
以下に行った3つの活動内容に関して詳細に記述する。
「目的」「方法」「成果」「課題」の4項目に関して記述している。
☆ 植生調査:
目的は、現状を知り記録として残すことだった。
記録として残す際に必要な項目については、エリア内の植生の現状把握という目的に従い、「樹種」とその「分布」とした。
この2項目を地図(手書き)に書き入れ、その際樹種は記号に直して表示した。エリアを東西に2分し、分担して各2名ずつが担当し、小林は両班のサポート(樹種の同定係)として調査を行った。
見られた樹種:コナラ、ソヨゴ、ネジキ、コバノミツバツツジ、モチツツジ、ヤマザクラ、カナメモチ、モウソウチク、ハチク、タカノツメ、フジ、ヒサカキ、アラカシ、シダ類、ヒイラギ
※気がついたことは欄外に書いた。(例:株立ちしている、枯れている、萌芽している、ナラ枯れ被害あり)
成果:
⑴5人で行った分、逆に個々人が躍動してくれ、思った以上に樹種に興味を持って取り組めたこと。
⑵調査を通して樹種の傾向が感覚的に捉えられたこと。
課題:
⑴斜面の情報をデータとして入れることが出来なかったこと。(天候条件が大きく異なるから。)
⑵エリア総面積を測るのを忘れていたこと。
☆廃材(言い方が気に食わないが。)の移動
目的は今後安全に活動をするための足場を作る為だった。運び出した材の利用法は検討すべきであると感じた。
活動エリア中央と東にの2カ所に溜めた。
成果:
⑴活動の足場の確保はできたこと。
課題:
⑴利用法について検討・議論の余地が大いにあるということ。
Ex.チップ化して土壌改良剤、透水性遊道、芝育成、竹炭、バンブーティー、農園芸マルチ材、堆肥化して法面緑化、ツルで束ねて荷物置き・ベンチ化etc
☆ 落ち葉掻き:
目的は林床に光を与えること、また堆肥作り。設置場所は倉庫側か山の入り口。設置容器作り。(宇佐美:担当)
次回の会議時に発表してもらう。
成果:
⑴行えたこと自体に意味があった。
課題:
⑴会議で話し合って行く予定。
以上です。
なかなか皆さんの予定が合わずに大勢の参加とはなりませんが、今後も楽しく安全にやっていきましょう!
活動日時:12月7日
活動時間:11時〜14時
活動メンバー:5人(全て2回生)
文責:小林
2013年11月02日
新体制のスタート

活動内容は、以下の通りです。
樹木の名前のクイズをしながら尾根沿いを歩き、北駐車場がらいつもの如く写真を撮りました。
いつ見ても美しいのどかな場所ですね、京田辺キャンパス近くは。
その後、北斜面に今後の活動エリアに黄色のテープを巻きました。
今後はこのエリアに絞り、活動を行います。
エリアの環境
⇒モウソウチク・ハチク林、コナラ・ソヨゴ二次林の混合林です。
被度は70〜80%で、モチツツジ・コバノミツバツツジ・ネジキなど花が奇麗な樹木もあります。
活動指針は以下の通りです。
1、植生調査をする(エリアの面積も測る)
2、間伐する
3、林床の観察、植樹など実験的な事をする
4、モニタリングをする
一番重要な事は、「みんなが楽しい」と思えることです。
楽しいというのを第一に、その上で、将来に向けて意味ある事を、環境サークルという中の1部会として、目的を明確にした上で活動し、学んでいきたいと思います。活動内容は、毎週行っている会議にて決定していこうと考えています。
「継続は力なり」
いよいよ蚊も減り、ひんやりした気温になってきましたので、活動日和の到来です!!
今後も月に1回のペースで活動を行っていきましょう。
集まれ!環シスのみんな、里山に。俺は決してここの山を見捨てない。
活動日:2013年11月2日
活動時間:13時〜14時半
活動メンバー:9人(2回生)
報告:小林慧人
2013年10月02日
10月2日の記事
こんばんは、更新率をあげるという様に書いていましたが、忘れてしまっていました。
まあ許してあげましょう!!
まずは、同志社大学京田辺キャンパスの裏山の近況、そして、その後に日本の森林について書きます。
☆近況
ナラ枯れによって枯死したコナラ(Quercus serrata)の個体数に関して正確には勘定していませんが、7月に予想していよりは枯死していない印象を受けます。つまり、最悪の事態は耐えたということでしょう。
ところで、少しびっくりする事が起きています。大学の関係者がして下さったであろうと推測していますが、コナラ枯死個体が一本伐採されていました。
学生だけではチェーンソーを使うのは危険ですし、カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)のマスアタックを受けて弱って枯れた(順序は逆かもしれませんが)ことは事実ですので、被害拡大を防ぐ為にも伐採して頂き本当にありがたい話です。
ただ、伐ったコナラを放ったらかしというのは正直疑問です。おそらく我々に後始末をしてもらおうという考えであると思いますが、ナラ枯れに関して正しい知識を持っている場合、伐採後にただちに燻蒸するという後始末までするのが自然な流れです。伐採する事で、突然倒れるという危険性は免れる事になりますが。
実際、間伐時を含めた伐採後の丸太がカシナガの拠点になるという研究例もあるくらいですから、処理方法には気を払った方が良いと考えます。
したがって、里山部会として行って行くべきことは、まず後始末をする事であると思います。
山の中は蚊が多く、スズメバチの仲間が徐々に増えてきた印象を受けます。先日、2時間山にいたため顔が晴れ上がるほど刺されたので正直なところ暫くは入りたくないですね(笑)
☆日本の森林
最近久々に本を読みました。研究室においてあった現代日本生物誌6「マツとシイ」という原田さん執筆の本です。
自分なりにまとめてみます。
日本の山は縄文時代から基本的には人が関わりをもってきたため、約50年前の燃料革命以降生活スタイルが急激に変化しました。
山からの恩恵を受けなくても生きていけるわけですから、手間のかかる山仕事をする人は当然減る訳です。
この本では、一般的に遷移という点で対極にある2つの樹木に関してそれぞれの性質を述べ、絵画や書物や写真を通して植生の変化があるということを述べています。登場人物のマツは土壌が肥沃でない場所でも生育する樹木です。
もう一方のシイは、少なくとも西日本では極相林であり、実は枝を伸ばす事においては他の照葉樹よりも長けているという点でパイオニア的性質も兼ね備えています。
もともとマツが多かった地域が、人が手を加えなくなった事で徐々に照葉樹林に変化していく様を写真を通して記述しており、新鮮な印象を受けました。
これからの日本の森林をどのようにしていくか考えるにあたって、やはり地域地域の取り組みが重要になってくると思います。
というのも、本書でも取り上げられていますが、地域によってこれまでの先人の森林の利用方が異なるからです。その歴史を学び、どうしていくのが現時点でベストな選択であるか考える必要があるのでしょう。
地域毎で考えて行く事になると、地域の繋がりが自ずと生まれます。核家族化が進んだことで地域の繋がりが薄くなっているといわれる現代において、地域の繋がりを取り戻すという意味を踏まえると地域単位で住民参画型の森林活動を行う意義はあります。
自分も地元の里山活動に参加することがありますが、毎回おじさんおばさんから積年の技を教えてもらえます。書物ではなく身振り手振りを交えて上の世代から受け継いだ技というのはまさに「遺産」となります。
中には口うるさい方もいらっしゃいます。そうやって色んな人生経験を持った人とふれあう機会を青年期までに得ているのと得ていないのでは社会に出たときに大きな差が生じる気がしています。
しかし、ただ単に活動すればいいという話ではありません。過去を学ぶ際には過去の文献や複数人に対して聞き取り調査、古写真などを利用します。この際、学術的に一連の資料から分析できる論文が書けるような人材が必要になります。
つまりどういうことかと言うと、地域の中でもピラミッド構造が成立している必要があるということです。アマチュアの自然に詳しい人と、専門家たるひとは区別できなければいけません。また、活動を継続して行くに際しては地域の盛り上げ役なる人の存在も必要ですし、色んな経歴を持つ人が気軽に参画できるコミュニティが必要になってきます。これらのコミュニティのなかで健全な(定義はあいまい)キャッチボールが行われるのが望ましい理想型だと考えます。
そして、地域の中でもどこをどうしてしていくのか共通理解をして活動していくべきでしょう。具体的には、ここは遷移に任せて鬱蒼とした照葉樹林にし、別の場所はマツ林を管理して行く、またある場所はツツジの花道をつくるなど。防災に力をいれるところであればある程度人が管理して行くことが必要となります。共通理解を得るには、やはり学校教育の中で森林に関する正しい知識は教えて行くべきであるでしょう。
遷移を進め自然植生に戻すべきなのか、遷移を食い止めクヌギなど落葉広葉樹林を残してこどもたちの昆虫採集の場所とするのか、何が正しいといのはありません。
正しいという”モデル”はありませんが、前にも書いているように、じっくりとその地域の歴史を振り返り考えて行く事が大切になってくると思います。
どうでしょうか。うまく話がまとまりませんが、日本の森林のあり方について少しは僕自身の中で光が見えてきたような気がしています。やはり書物を読み、色んな人に話を聞き、自分で考えることが重要なのですね。
以上です。
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
まあ許してあげましょう!!
まずは、同志社大学京田辺キャンパスの裏山の近況、そして、その後に日本の森林について書きます。
☆近況
ナラ枯れによって枯死したコナラ(Quercus serrata)の個体数に関して正確には勘定していませんが、7月に予想していよりは枯死していない印象を受けます。つまり、最悪の事態は耐えたということでしょう。
ところで、少しびっくりする事が起きています。大学の関係者がして下さったであろうと推測していますが、コナラ枯死個体が一本伐採されていました。
学生だけではチェーンソーを使うのは危険ですし、カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)のマスアタックを受けて弱って枯れた(順序は逆かもしれませんが)ことは事実ですので、被害拡大を防ぐ為にも伐採して頂き本当にありがたい話です。
ただ、伐ったコナラを放ったらかしというのは正直疑問です。おそらく我々に後始末をしてもらおうという考えであると思いますが、ナラ枯れに関して正しい知識を持っている場合、伐採後にただちに燻蒸するという後始末までするのが自然な流れです。伐採する事で、突然倒れるという危険性は免れる事になりますが。
実際、間伐時を含めた伐採後の丸太がカシナガの拠点になるという研究例もあるくらいですから、処理方法には気を払った方が良いと考えます。
したがって、里山部会として行って行くべきことは、まず後始末をする事であると思います。
山の中は蚊が多く、スズメバチの仲間が徐々に増えてきた印象を受けます。先日、2時間山にいたため顔が晴れ上がるほど刺されたので正直なところ暫くは入りたくないですね(笑)
☆日本の森林
最近久々に本を読みました。研究室においてあった現代日本生物誌6「マツとシイ」という原田さん執筆の本です。
自分なりにまとめてみます。
日本の山は縄文時代から基本的には人が関わりをもってきたため、約50年前の燃料革命以降生活スタイルが急激に変化しました。
山からの恩恵を受けなくても生きていけるわけですから、手間のかかる山仕事をする人は当然減る訳です。
この本では、一般的に遷移という点で対極にある2つの樹木に関してそれぞれの性質を述べ、絵画や書物や写真を通して植生の変化があるということを述べています。登場人物のマツは土壌が肥沃でない場所でも生育する樹木です。
もう一方のシイは、少なくとも西日本では極相林であり、実は枝を伸ばす事においては他の照葉樹よりも長けているという点でパイオニア的性質も兼ね備えています。
もともとマツが多かった地域が、人が手を加えなくなった事で徐々に照葉樹林に変化していく様を写真を通して記述しており、新鮮な印象を受けました。
これからの日本の森林をどのようにしていくか考えるにあたって、やはり地域地域の取り組みが重要になってくると思います。
というのも、本書でも取り上げられていますが、地域によってこれまでの先人の森林の利用方が異なるからです。その歴史を学び、どうしていくのが現時点でベストな選択であるか考える必要があるのでしょう。
地域毎で考えて行く事になると、地域の繋がりが自ずと生まれます。核家族化が進んだことで地域の繋がりが薄くなっているといわれる現代において、地域の繋がりを取り戻すという意味を踏まえると地域単位で住民参画型の森林活動を行う意義はあります。
自分も地元の里山活動に参加することがありますが、毎回おじさんおばさんから積年の技を教えてもらえます。書物ではなく身振り手振りを交えて上の世代から受け継いだ技というのはまさに「遺産」となります。
中には口うるさい方もいらっしゃいます。そうやって色んな人生経験を持った人とふれあう機会を青年期までに得ているのと得ていないのでは社会に出たときに大きな差が生じる気がしています。
しかし、ただ単に活動すればいいという話ではありません。過去を学ぶ際には過去の文献や複数人に対して聞き取り調査、古写真などを利用します。この際、学術的に一連の資料から分析できる論文が書けるような人材が必要になります。
つまりどういうことかと言うと、地域の中でもピラミッド構造が成立している必要があるということです。アマチュアの自然に詳しい人と、専門家たるひとは区別できなければいけません。また、活動を継続して行くに際しては地域の盛り上げ役なる人の存在も必要ですし、色んな経歴を持つ人が気軽に参画できるコミュニティが必要になってきます。これらのコミュニティのなかで健全な(定義はあいまい)キャッチボールが行われるのが望ましい理想型だと考えます。
そして、地域の中でもどこをどうしてしていくのか共通理解をして活動していくべきでしょう。具体的には、ここは遷移に任せて鬱蒼とした照葉樹林にし、別の場所はマツ林を管理して行く、またある場所はツツジの花道をつくるなど。防災に力をいれるところであればある程度人が管理して行くことが必要となります。共通理解を得るには、やはり学校教育の中で森林に関する正しい知識は教えて行くべきであるでしょう。
遷移を進め自然植生に戻すべきなのか、遷移を食い止めクヌギなど落葉広葉樹林を残してこどもたちの昆虫採集の場所とするのか、何が正しいといのはありません。
正しいという”モデル”はありませんが、前にも書いているように、じっくりとその地域の歴史を振り返り考えて行く事が大切になってくると思います。
どうでしょうか。うまく話がまとまりませんが、日本の森林のあり方について少しは僕自身の中で光が見えてきたような気がしています。やはり書物を読み、色んな人に話を聞き、自分で考えることが重要なのですね。
以上です。
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
2013年08月19日
8月19日の記事
こんちには、今日は活動日でした。
森の中はとても涼しく、クモの巣の多さと蚊に刺される事を除けば、冷房を付けているかの様な快適さです。
テストが終わり2週間が経ち、久々に山に足を運びましたが、エリア内尾根沿いのコナラ枯死個体が3本増えていました。
また木の根元には大量のフラスが溜まっており、来年度には8〜9割りのコナラが枯死すると予想を立てています。
(明確な根拠はありませんが)
今日の目的は
1、カシナガトラップの確認
2、虫取り
3、竹を使った何かを作る(個人的)
でした。
まず、1についてです。
残念な事に、2つとも失敗していました。
1つは、キャップを付けたままにしていたという初歩的な失敗、もう1つは、受け皿となるペットボトルがなくなっていた事です。
失敗の原因としましては、長期間放っておいた事でしょうか。
来年度に向けてのいい教訓となりました。
また、やっている事に関しての理解のレベルを合わせる事も大事だと思います。
次に、2についてです。
捕虫網を持っていったものの今年は樹液が少なく、昨年度のようにカブトムシが集まるといった事はありませんでした。
樹液の出る原因と雨量には何かしら関係性があるのでしょう。
最後に、3についてです。
これに関しては、ハチクを切り、節毎に切り分け、小林と二回生女子が1つずつ持って帰りました。
用途としましては、ペン立てを考えています。
森林と生活が切り離されている今において、こういう事をする意義は多いにあると思います。
メンバーが少なく少し寂しい気もします。
里山部会がいつしかにぎわうようこちらも努力ですね。
以上です。
活動時間:10:00〜12:00
活動メンバー:8人(三回生2人、二回生6人、一回生0人)
報告:小林慧人
2013年08月17日
8月17日の記事
里山部会はいよいよ明後日ということですが、山はどうなっているのでしょうか?
テストが終わってから一回も大学の方へ行っていないので、ナラ枯れの進行具合など気になります。
今日は昼から夜まで珍しく自宅なので、久々に何か書こうかと思います。
案外自宅にいると妙に落ち着かないというか家族の存在が気になるというか。。。
無駄な時間を過ごしてしまっている気がするので、せめて有意義な事を書こうかと思います。
将来の森林のお話。素人なりに考えている事。
確かに僕は虫が好きで、捕虫網を振り回してチョウを追いかける時、またいい写真が撮れた時、生きがいを感じています。
しかし、ただ虫が好きな人ではいたくないと思っています。そのため最近はナチュラリストを推しています。(周りの人からは定義があいまいだの言われますが。)
日本の森を論ずる際、将来的に大きな場で論ずる際、自分の森林観が虫に支配されていては視野が狭く一般の人に耳を傾けてもらえるような話はできないと思うからです。森林の生態系を捉えるマクロな視点を持って森林を見る。また、森林の裏に潜む世の中の動き、お金の動きにも敏感になる必要があると思っています。
地域によって、森林利用の歴史、風習は違います。したがって、全国一律森林モデルのようなものを作るのは避けるべきで、それよりもは地域毎に森林と向き合い、生活の身近な存在として森林を捉える人材育成、そのための教育を施していく事が、究極的な目標なのではないでしょうか。
続く。
最近知識面でのinputが増えていないと感じています。まあ9月にご期待ですね。
今は、今できる事をする。フィールドへ出て、毎日色んな事を感じる感覚を研ぎ澄ませたいと思っている次第です。
フィールドでしか鍛えられない感覚と、本、論文からしか得られない知識。これらを同時並行で鍛えていきましょう!
(環境問題を学ぶ学生としてはどうなのでしょうか。フィールド重視を嫌う方もいらっしゃるようですが笑)
理工学部環境システム学科
小林慧人