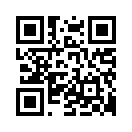2013年07月20日
7月20日の記事
こんにちは、今日は活動日でした。
今日は、かねての望みであった、カシナガトラップを作って実際に取り付けてみました。
皆さんお忙しいのでしょうか、今日は3回生が多かったですね。
即席形のトラップですが、案外様になっているようです。
徐々に枯死個体が増えつつある、京田辺キャンパス裏山ですのできっとカシナガは引っかかってくれるでしょう。
楽しみです。
外は暑いですが森の中はヒンヤリ。これぞ夏の賢い過ごし方ではないでしょうか。
ただ蚊対策は必要ですね。
今日のところはここまで)^o^( 眠たいですね笑
<今日の裏山>
コナラの樹皮から樹液が垂れています。ということで、カナブンが多く集まっている木もありました。
今日新たに一本、裏山でコナラ枯死木の発見がありましたね。
倉庫の奥、細いコナラでした。(なんてあいまいな・・・)
活動時間:13:00~15:00
活動メンバー:6人(3回生 3人、2回生 3人)
(途中まで3回生 2人、2回生 2人、1回生 1人)
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
2013年07月15日
7月15日の記事
こんばんは。今日も何かつらつら書こうかと思います。
では、一つお話いきます。「ノギスについて」
学科の実験で直尺やノギスやマイクロメータの測定精度を考える実験がありました。
お陰様で、昨日はレポートを書いていてほとんど寝れませんでしたが。。。
ただ感動した法則がありました。それは「誤差伝播の法則」です。
詳しい事はネット検索をかければ出てきますので書きませんが、誤差の伝播、納得のいく法則です。
ただ、これにも裏があるのかもしれませんね。いい面しかない、という事はこの世界ありませんもんね。
ところで、ノギスですが、これは樹木の短枝の太さを計る際に用いたりします。同志社大学裏山のホットな話題ですと、タケ(モウソク、ハチク、マダケ)の枝(この表現は正しい??)の太さを測る際に用います。
0.05mmまで測定可能という事です。
では、次のお話「伝播がらみのお話」です。(無理やり里山と絡めていきます。)
昨日、「人生の目的は何なのか」、そんなレポートを出すようバイト先からの指示がありました。そんなわけで色々と考えていましたが、素敵な考え方に出会えたような気がしています。
地質学的スケールももって人類を俯瞰していますと、なんとも自分の存在のちっぽけさを感じてしまいます。
ちょっと悲しくなったときは空を見上げてみよう。こんなにちっぽけな存在じゃないか。という形で自分を励ます手段として使われいたりします。
それはさておき、そんな事を聞くと、ちっぽけな存在なのだから自分なんて存在しなくてもいいではないかという気持ちになってしまっても不思議ではありません。特に自分の周りには大学に自分がいる存在意義について思い悩んでいる方も少なからずいらっしゃる気もしています。
現在こうして地球で生きている自分の存在を真っ向から否定する、そんな人にはこんな事をお伝えしたい。
「精神の伝播」があるんだよ。
どういうことでしょうか?確かに自分と言う存在は数十年で消え、100年後の世界を覗くとほとんどの人は、自分の影、形が何も残っていないという事に気づきます。ただ、これは現在から100年後に一気に視点を移動させてしまったが故に感じてしまう事なのです。現在から100年後まで線をつないで見てみましょう。
すると、何が見えてくるか。生き物はDNAの上に乗っているモノに過ぎないという考え方の基で考えると、単純な話ではDNAという形で自分が残っていく事も考えられます。また、自分の考え方、精神というものは、自然と出会った人みんなに伝わって残っていきます。この点で「精神の伝播」の考え方が成り立ちます。
ある人の精神が、他人にどんな形であれ影響を与え、無限大に広がっていくことでしょう。
今の自分は確かに不完全であります。ただ完璧な人はいません。劣等感を味わったり、自分の存在が分からなくなった時、「精神の伝播」を思い出していただきたいものです。
そして、これは森林利用に関しても当てはまります。昔の人の生活の一部であった里地里山。
彼らの精神は今どこに漂っているのでしょうか。その精神を僕らがかき集め、昔とは違った形で山と向き合っていく必要があるのではないでしょうか。そして、受け取った精神を、新たな形で後世に伝播させていきたいですね。
どうでしょうか。誤差の伝播から、こんなに話が広がって行きました。
精神活動、内面的ワーク。これほど楽しいものはありません。1週間後見たときには、こんな考え方は古いな。
そう思えるように日々進化していきたいと思いますね。
文: 小林慧人
では、一つお話いきます。「ノギスについて」
学科の実験で直尺やノギスやマイクロメータの測定精度を考える実験がありました。
お陰様で、昨日はレポートを書いていてほとんど寝れませんでしたが。。。
ただ感動した法則がありました。それは「誤差伝播の法則」です。
詳しい事はネット検索をかければ出てきますので書きませんが、誤差の伝播、納得のいく法則です。
ただ、これにも裏があるのかもしれませんね。いい面しかない、という事はこの世界ありませんもんね。
ところで、ノギスですが、これは樹木の短枝の太さを計る際に用いたりします。同志社大学裏山のホットな話題ですと、タケ(モウソク、ハチク、マダケ)の枝(この表現は正しい??)の太さを測る際に用います。
0.05mmまで測定可能という事です。
では、次のお話「伝播がらみのお話」です。(無理やり里山と絡めていきます。)
昨日、「人生の目的は何なのか」、そんなレポートを出すようバイト先からの指示がありました。そんなわけで色々と考えていましたが、素敵な考え方に出会えたような気がしています。
地質学的スケールももって人類を俯瞰していますと、なんとも自分の存在のちっぽけさを感じてしまいます。
ちょっと悲しくなったときは空を見上げてみよう。こんなにちっぽけな存在じゃないか。という形で自分を励ます手段として使われいたりします。
それはさておき、そんな事を聞くと、ちっぽけな存在なのだから自分なんて存在しなくてもいいではないかという気持ちになってしまっても不思議ではありません。特に自分の周りには大学に自分がいる存在意義について思い悩んでいる方も少なからずいらっしゃる気もしています。
現在こうして地球で生きている自分の存在を真っ向から否定する、そんな人にはこんな事をお伝えしたい。
「精神の伝播」があるんだよ。
どういうことでしょうか?確かに自分と言う存在は数十年で消え、100年後の世界を覗くとほとんどの人は、自分の影、形が何も残っていないという事に気づきます。ただ、これは現在から100年後に一気に視点を移動させてしまったが故に感じてしまう事なのです。現在から100年後まで線をつないで見てみましょう。
すると、何が見えてくるか。生き物はDNAの上に乗っているモノに過ぎないという考え方の基で考えると、単純な話ではDNAという形で自分が残っていく事も考えられます。また、自分の考え方、精神というものは、自然と出会った人みんなに伝わって残っていきます。この点で「精神の伝播」の考え方が成り立ちます。
ある人の精神が、他人にどんな形であれ影響を与え、無限大に広がっていくことでしょう。
今の自分は確かに不完全であります。ただ完璧な人はいません。劣等感を味わったり、自分の存在が分からなくなった時、「精神の伝播」を思い出していただきたいものです。
そして、これは森林利用に関しても当てはまります。昔の人の生活の一部であった里地里山。
彼らの精神は今どこに漂っているのでしょうか。その精神を僕らがかき集め、昔とは違った形で山と向き合っていく必要があるのではないでしょうか。そして、受け取った精神を、新たな形で後世に伝播させていきたいですね。
どうでしょうか。誤差の伝播から、こんなに話が広がって行きました。
精神活動、内面的ワーク。これほど楽しいものはありません。1週間後見たときには、こんな考え方は古いな。
そう思えるように日々進化していきたいと思いますね。
文: 小林慧人
2013年07月05日
7月5日の記事
こんにちは。外は快晴で蒸し暑く、中は明るく涼しいですね。
こんな時は、みんなで虫採り! といいたいところです。
今年はナラ枯れ木の影響で、Quercusから樹液出ていますので、確実に甲虫類は期待できそうです)^o^(
夏休みは遠方で昆虫採集、塾のバイトとなりそうで、同志社裏山とのかかわりが消えそうで辛いところです。
教室ではマイマイガ♂が飛び交っていることも。
残念ながら、本来僕の対局の分野と以前は位置づけていた物理のレポートで最近は四苦八苦です。
大学生になって気が付きましたが、僕の認識不足でして、生態学を勉強するにしても諸モデルを学ぶ必要性があって、数学は本当に大切です!
もちろん数式であらわされた物理学も大切です。
最近は現象のモデル化だけでなく、実験を通してモデル化することが研究の基本になっているようです。
思考能力を養うという点、この学科の実験(話さずに行う実験)は素晴らしいと思っています。(自分だけか。。笑)
どうせといえば失礼ですが、インピーダンスなんて定義は一年もしたら忘れているものです。それが人間の脳というものです。
それよりも、独力で考え抜いて、それを他人に分かりやすい形で、レポートという形にまとめることに大きな意義があると思っています。
それにしても難しいですね!! でも楽しい。ワクワクします~
終わらせて、珍しい蝶の多い精華町にぶらりしたいものです。
p.s.
感覚的な話ですが、最近ふと思ったこと。
ヒトはあくまで生き物です。こんなにPCを凝視していたらいつか異常をきたすのではないでしょうか?
チンパンジーが一日中PCに向かっていたら、普通に考えて心配しますよね。
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
2013年06月21日
ナラ枯れ 現状
久々の投稿となります。
最近、久々に色々と考えさせられる日々を過ごしている気がします。
人にはそれぞれのペースがあります。それをどう評価すればよいのかは難しいですよね。
そもそも評価なんてする必要がないのかもしれません。人それぞれですから。
例えば、テスト一つとってもなかなか深いものです。
点数をもって人を容易に評価してしまう日本の教育の現状を僕はあまり好みません。
ただ残念ながら、僕が教育者の立場にたてば、テストで評価してしますのでしょう。。。
大学でも、テストの度に「覚えてしまえ!」と言っている人は多いようですが、少なくとも自分の評価基準の中ではそのような考え方は受け入れがたいものです。先生方は、覚えているだけでは点数は取れないように作っているとおっしゃいますが、実際は取れてしまう気もします。
覚える作業、そんな勉強していても何も糧ににならない気がしています。成績は取っても、何かむなしい気持ちになってしまいます。2日後には忘れてしまいますもんね。
正直言って、大学が学生に課す量は多いです。深めようとする間に次々とやってくる。
これでは、勉強がTo Doリストのように作業化してしまうでしょう。本来、勉学ってそんなものではないはずです。この事態、どうしていけばよいのでしょうかね・・・
自分は、将来日本の森林のあり方を変えるという軸がありますので、その軸を大切に勉強していきたいものです。
はい(^'^)
同志社裏山でのナラ枯れの現状です。
先日、カシナガが樹内へ入った跡を示す穴「穿入孔(entry hole)」に爪楊枝を差しましたが、梅雨の中でも爪楊枝は一本も抜けていませんでした。
樹液が多く出ていたので、今年はカブトムシやクワガタムシといった甲虫が姿を見せてくれるはずです。
その点は少し楽しみですね。
あっ、マイマイガ多いですね。でも大丈夫!基本的には刺しませんので。(1齢幼虫は毛に毒性ある?)
今後も見守っていきたいと思います。
報告:小林慧人
2013年06月02日
6月2日の記事
こんばんは。
昨日、里山部会での活動がありました。
一回生も一人来てくれたので良かったですね。そのかわり・・・
昨年度に間伐した空間にどのような植物が顔を出しているのでしょうか?
出てきていましたね。
「あぁ、出てきている!」で終わっちゃいそうですね・・・
非常に難しい話で、真剣にやるのであれば写真を撮り、一つ一つ数え、種を同定し・・・となりますが、
そんなことをする必要性があるのか自分でもよく分かりません。
まあ、長期的に見ていけばそれなりに興味深いものになると思います。
次は、ナラ枯れの話。
最近、興味があるので深く掘り下げるために、あらゆる論文を一通り読んでいると楽しいです。
カシナガがブナ科樹木に入る事を「穿入」といいますがその穴の事を、英語ではentry holeと言ったり・・・
まあそれはいいとして、昨日はその穴に爪楊枝を差し込んでみました。
写真では見えずらいですかね。。。
意図は勿論ありますが、楊枝を差し込む事で、今まで気にもしてこなかった小さな穴に注目できることが良い点でしょうか。
飛び込んだ方向が一目瞭然にもなりましたね。
一つの穴から、5~10頭のカシナガが出てくると言われていますので
35穴あったコナラからは単純計算で、175~350頭出てくることになります。
そういえば、枯死木が一本見つかりました。
同志社裏山は、土地がやせているのでその分細いコナラが多く
重度なナラ枯れは免れたのでしょか?
自然は不思議。その不思議に人間が日々あれこれ解釈を加える。
研究する。ヒトは何のために研究なんてやるのか?
それは好奇心でしょう。
好奇心、それは「奇を好む心」と書きます。
つまり「珍しい事、不思議な事を好む心」です。
いやぁ、素敵だなぁ。こう思っている自分は変人なんでしょうかね。。。
そんな世界にどっぷり浸かりたい。そんな事を思う日々です。
活動時間:11:00~13:30
活動場所:校内ゴルフ場裏山
参加人数:8人(4回一人 3回一人 2回五人 1回一人)
報告:小林