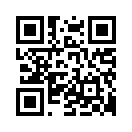2014年02月18日
里山活動という矛盾
☆はじめに☆
こんにちは。本日も教習所から小林です。
(これを書く意図は、後で読み返した時、教習所で本を読んで隙間時間で文章を作っていたぞ!ということを自分に思い出させることです。誠に勝手な話ですが(笑))
今日は、以前も触れた「里山活動に関わる私の矛盾」のお話です。
☆土地を利用することの矛盾☆
始めに言っておきましょう。以下のように、私は自己矛盾を感じておりますが、決して活動自体に後ろめたさを感じているわけではありません。
では、何が矛盾か、まずはそれについて書きます。
私は、前回(昨日2/16)の投稿にて、土地利用の歴史を知ることこそが、活動を行うにあたって重要だという趣旨の内容を書きました。
私も含め、部員には社会に出てからも何かしらの形で自然と直接関わっていただきたいと思っています。
理由としては、環境を学ぶ学生は知識が豊富であるが故に、どうしても美しい言葉を並べて、あたかも自然を分かったような気になってしまいがちだということが挙げられます。特に、私のように都市環境にすっかり慣れ親しんだ人ほど気をつけるべきだと感じます。全ての人がフィールドにも出なければならないという決まりはありませんが、フィールドに意識を持つこともやはりこれからの時代、必要不可欠となるでしょう。
大学内の山であれば、大学の施設課から許可が下りた以上、ある程度好きなように活動を行うということでよいと考えていますが、社会に出てからは(つまり大学外の活動地)特に活動地となる地域の方々の意向を最優先させなくてはなりません。
しかし、この私見には大きな誤りであるのです。以下の引用を通して考えます。
「土地の歴史という点から里山保全の動きをとらえなおしてみると、里山保全を担っている都市住民や大学は、いったん里山を開発した土地の上で自分たちの生活を営み、里山保全を主張するという矛盾を抱えているからである。」(※1)
ここで言いたい矛盾とは、まさに上記の引用文中の「矛盾」のことです。
☆引用に対する解釈☆
まさに上記は私たちの現状を捉えた引用文であると言えます。
ただ、これを言われれば反論する術がないのではないでしょうか。あたかも、教授に論破された時のように。
このような時はどうすればよいのでしょうか。やはり、私たちがこのことを認識することが最も大切なこととなるでしょう。意識の片隅に入れた上で活動するのと、しないのとでは、一見微差のように思えますが、「塵も積もれば山」という諺の如く、微差が大差を生むのではないか(微差力という本も出回っていますね。)、そのような気がします。
里山活動では、参加者がそれぞれ何かしら「理想の里山」のイメージを無意識のうちに描いて活動しています。私の場合は、スプリングエフェメラルの充実し、ゼフィルスが舞うといった景観です。
里山とは、もともと人の手が加えられた人里近くの山のことですが、これだけ里山活動に対して様々な方面から人が集うと、里山に対する解釈は拡大を続けるでしょう。これは、英語が世界規模へと広がるに従って様々な解釈が加えられ、多様化していくことと似ているような気がします。
同じ「山」と名前が与えれるところでも、そこに根付く歴史、先人の気持ちは実に様々で一括りすることは出来ません。里山という言葉に関しても、近年になって勝手に広まった言葉に過ぎず、例えば「里山100選」と名付けられたからといって特にその景観には何も変化はないのです。
お化粧をすれば綺麗に変身する、アクセサリーを付けて髪を染めセットすれば格好良くなるといったように、この世界は装飾であふれています。
ただの山なのに、そこに人の惹き付けられるような「言葉」という飾りつけを行い、価値を与えようとするのが我々人間の性ですから、仕方のないことです。
だから、私たちはそのような言葉、ここでいうなら「里山」という美しい言葉に、惑わされ本質を失わないよう、地域を大切に取り組んでいくべきなのです。
矛盾なんぞ、世の中溢れているのですから。
以上です。
(※1:里山学のまなざし 丸山徳氏、宮浦富保編 昭和堂 2009 初版 p.143)
投稿:小林
こんにちは。本日も教習所から小林です。
(これを書く意図は、後で読み返した時、教習所で本を読んで隙間時間で文章を作っていたぞ!ということを自分に思い出させることです。誠に勝手な話ですが(笑))
今日は、以前も触れた「里山活動に関わる私の矛盾」のお話です。
☆土地を利用することの矛盾☆
始めに言っておきましょう。以下のように、私は自己矛盾を感じておりますが、決して活動自体に後ろめたさを感じているわけではありません。
では、何が矛盾か、まずはそれについて書きます。
私は、前回(昨日2/16)の投稿にて、土地利用の歴史を知ることこそが、活動を行うにあたって重要だという趣旨の内容を書きました。
私も含め、部員には社会に出てからも何かしらの形で自然と直接関わっていただきたいと思っています。
理由としては、環境を学ぶ学生は知識が豊富であるが故に、どうしても美しい言葉を並べて、あたかも自然を分かったような気になってしまいがちだということが挙げられます。特に、私のように都市環境にすっかり慣れ親しんだ人ほど気をつけるべきだと感じます。全ての人がフィールドにも出なければならないという決まりはありませんが、フィールドに意識を持つこともやはりこれからの時代、必要不可欠となるでしょう。
大学内の山であれば、大学の施設課から許可が下りた以上、ある程度好きなように活動を行うということでよいと考えていますが、社会に出てからは(つまり大学外の活動地)特に活動地となる地域の方々の意向を最優先させなくてはなりません。
しかし、この私見には大きな誤りであるのです。以下の引用を通して考えます。
「土地の歴史という点から里山保全の動きをとらえなおしてみると、里山保全を担っている都市住民や大学は、いったん里山を開発した土地の上で自分たちの生活を営み、里山保全を主張するという矛盾を抱えているからである。」(※1)
ここで言いたい矛盾とは、まさに上記の引用文中の「矛盾」のことです。
☆引用に対する解釈☆
まさに上記は私たちの現状を捉えた引用文であると言えます。
ただ、これを言われれば反論する術がないのではないでしょうか。あたかも、教授に論破された時のように。
このような時はどうすればよいのでしょうか。やはり、私たちがこのことを認識することが最も大切なこととなるでしょう。意識の片隅に入れた上で活動するのと、しないのとでは、一見微差のように思えますが、「塵も積もれば山」という諺の如く、微差が大差を生むのではないか(微差力という本も出回っていますね。)、そのような気がします。
里山活動では、参加者がそれぞれ何かしら「理想の里山」のイメージを無意識のうちに描いて活動しています。私の場合は、スプリングエフェメラルの充実し、ゼフィルスが舞うといった景観です。
里山とは、もともと人の手が加えられた人里近くの山のことですが、これだけ里山活動に対して様々な方面から人が集うと、里山に対する解釈は拡大を続けるでしょう。これは、英語が世界規模へと広がるに従って様々な解釈が加えられ、多様化していくことと似ているような気がします。
同じ「山」と名前が与えれるところでも、そこに根付く歴史、先人の気持ちは実に様々で一括りすることは出来ません。里山という言葉に関しても、近年になって勝手に広まった言葉に過ぎず、例えば「里山100選」と名付けられたからといって特にその景観には何も変化はないのです。
お化粧をすれば綺麗に変身する、アクセサリーを付けて髪を染めセットすれば格好良くなるといったように、この世界は装飾であふれています。
ただの山なのに、そこに人の惹き付けられるような「言葉」という飾りつけを行い、価値を与えようとするのが我々人間の性ですから、仕方のないことです。
だから、私たちはそのような言葉、ここでいうなら「里山」という美しい言葉に、惑わされ本質を失わないよう、地域を大切に取り組んでいくべきなのです。
矛盾なんぞ、世の中溢れているのですから。
以上です。
(※1:里山学のまなざし 丸山徳氏、宮浦富保編 昭和堂 2009 初版 p.143)
投稿:小林