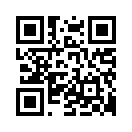2014年04月20日
里山の蝶
こんばんは、今日は蝶相の話題を。
京田辺校地内では案外多くの蝶が生息しています。
校内にはクスノキが多く植えられているのでアオスジアゲハは初夏多く飛びます。アゲハチョウ科は他にアゲハやキアゲハ、裏山では、カラスアゲハを見かけます。
また、各種タテハチョウ科(アカタテハ、ヒメアカタテハ、キタテハ、ルリタテハ)やサトキマダラヒカゲは建物の近くで飛び回ったり、日向ぼっこをしています。勿論、テングチョウもたまに見られます。
校内では人の目につくところではアブラナ科植物が少なく、そのせいあってかシロチョウ科(モンシロチョウやキチョウ、モンキチョウ)は見かけません。裏山ではよく見かけます。
シジミチョウ科はヤマト、ベニ、ツバメ、ムラサキがよく見られ、ゼフィルスはアカシジミとミズイロオナガシジミしか見られません。食草も植わってませんので当然ですが。。。
ヒョウモンチョウ科では、ツマグロヒョウモンを裏山で見かけるくらいで少ないのが実情です。
セセリチョウ科では、キマダラとイチモンジしか採れていません。今年はもう少し種数を増やしたいものです。やはりイネ科が多く植わるゴルフ場近くの斜面が狙い目でしょうか。
期待しているのは、京都でも少しずつ顔を出している南方系の蝶、ミカドアゲハ。筒城宮の跡地の斜面にオガタマの木が数本並んでいるので、いつかは繁殖すると思っています。今の所校内はど普通種しかおらず刺激的ではありませんので。笑
以上。
投稿;小林
京田辺校地内では案外多くの蝶が生息しています。
校内にはクスノキが多く植えられているのでアオスジアゲハは初夏多く飛びます。アゲハチョウ科は他にアゲハやキアゲハ、裏山では、カラスアゲハを見かけます。
また、各種タテハチョウ科(アカタテハ、ヒメアカタテハ、キタテハ、ルリタテハ)やサトキマダラヒカゲは建物の近くで飛び回ったり、日向ぼっこをしています。勿論、テングチョウもたまに見られます。
校内では人の目につくところではアブラナ科植物が少なく、そのせいあってかシロチョウ科(モンシロチョウやキチョウ、モンキチョウ)は見かけません。裏山ではよく見かけます。
シジミチョウ科はヤマト、ベニ、ツバメ、ムラサキがよく見られ、ゼフィルスはアカシジミとミズイロオナガシジミしか見られません。食草も植わってませんので当然ですが。。。
ヒョウモンチョウ科では、ツマグロヒョウモンを裏山で見かけるくらいで少ないのが実情です。
セセリチョウ科では、キマダラとイチモンジしか採れていません。今年はもう少し種数を増やしたいものです。やはりイネ科が多く植わるゴルフ場近くの斜面が狙い目でしょうか。
期待しているのは、京都でも少しずつ顔を出している南方系の蝶、ミカドアゲハ。筒城宮の跡地の斜面にオガタマの木が数本並んでいるので、いつかは繁殖すると思っています。今の所校内はど普通種しかおらず刺激的ではありませんので。笑
以上。
投稿;小林
2014年04月19日
春の新歓 山菜パーティー
こんばんは。小林です。
さて、本日4月18日に行われた里山部会新歓の振り返りを行いたいと思います。
まずは、本日の流れのおさらいから。
☆スケジュール
10時 山集合
10時45分 1限終わりの1回生をお迎え
12時30分 山から切り上げ→畑へ
12時40分 2限終わりの1回生をローソン前でお迎え
15時 終了予定
そして、各活動に対するコメントを掲載します。
☆山での活動
タケノコ取り:今年は少なかったです。モウソウチクは言うまでもなく、ハチク、マダケもダメでした。昨年度、豊作だったため、今年度は少ないという考え方が妥当でしょう。自然って凄いな、そう実感した次第であります。ある化学物質が分泌され、それがスイッチとなって地下で繋がる竹は地表面に我々人間の目に見える形で示してくれているのでしょう。
タカノツメ採り:高枝ばさみが大活躍。参加者皆で相当量を摘みました。
1回生への里山案内:2人に対して里山部会のお決まりの尾根コースを案内。大学の校内にこんな環境があるのだと驚いていました。因に、僕は3年前先輩に連れて行っていただいたとき、大学内で楽しい場所ができたと思いましたね。
☆畑での活動
タンポポ、クズ、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、ヨモギ、アケビ、ノイバラを採り山菜パーティー:まだクズが少なかったことが残念でしたが色んな種類にチャレンジできた事が成果です。
☆安全対策
服装、天ぷら火災注意:準備不足が露呈しました。安全に行えたことは参加者皆の協力があったからです。
☆必要なもの
天ぷら粉、鍋、油、カメラ、油処理に必要なもの、紙ヤスリ(竹用)、高枝バサミ:紙ヤスリは必要品でした。
<反省会>
☆良かった点
環境団体らしきことができ、何より、一回生が楽しんでくれた事が収穫。山で一回生が来る前に一回りし、状況把握できたことは良かった。
☆悪かった点
準備不足。畑の整備をするべきで座る所は確保したい。(後輩に残すもの)立ちっぱなしはしんどいので、ブルーシートを確保する。
→備品の購入が必要。(鋸、ブルーシート)
という感じですが、やはり山菜パーティーがないと春は始まりません。春の幸を噛み締め、ほんのりとした苦みを感じることが何より大切なのではないでしょうか。今年度は、新たな企画を盛り込み、その分準備不足で、多大な迷惑を被った方も多くいたことでしょう。
それでも、相互に助け合うという精神は、社会人に必要な資質の一つであり、一日通して皆さんの能力の高さに感謝ばかりでした。
このサークルは表に出る活動はしていませんが、素晴らしく、未来への提言を含めた面白い企画を盛り込むサークルであると信じています。
今日は、みんなと山菜を食えて良かった。ただそれだけす。
活動場所:ゴルフ場奥の山、畑部会の畑
活動メンバー:1回生5人、2回生1人、3回生8人、4回生1人、OB1人
報告:遂に3回生になった小林
さて、本日4月18日に行われた里山部会新歓の振り返りを行いたいと思います。
まずは、本日の流れのおさらいから。
☆スケジュール
10時 山集合
10時45分 1限終わりの1回生をお迎え
12時30分 山から切り上げ→畑へ
12時40分 2限終わりの1回生をローソン前でお迎え
15時 終了予定
そして、各活動に対するコメントを掲載します。
☆山での活動
タケノコ取り:今年は少なかったです。モウソウチクは言うまでもなく、ハチク、マダケもダメでした。昨年度、豊作だったため、今年度は少ないという考え方が妥当でしょう。自然って凄いな、そう実感した次第であります。ある化学物質が分泌され、それがスイッチとなって地下で繋がる竹は地表面に我々人間の目に見える形で示してくれているのでしょう。
タカノツメ採り:高枝ばさみが大活躍。参加者皆で相当量を摘みました。
1回生への里山案内:2人に対して里山部会のお決まりの尾根コースを案内。大学の校内にこんな環境があるのだと驚いていました。因に、僕は3年前先輩に連れて行っていただいたとき、大学内で楽しい場所ができたと思いましたね。
☆畑での活動
タンポポ、クズ、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、ヨモギ、アケビ、ノイバラを採り山菜パーティー:まだクズが少なかったことが残念でしたが色んな種類にチャレンジできた事が成果です。
☆安全対策
服装、天ぷら火災注意:準備不足が露呈しました。安全に行えたことは参加者皆の協力があったからです。
☆必要なもの
天ぷら粉、鍋、油、カメラ、油処理に必要なもの、紙ヤスリ(竹用)、高枝バサミ:紙ヤスリは必要品でした。
<反省会>
☆良かった点
環境団体らしきことができ、何より、一回生が楽しんでくれた事が収穫。山で一回生が来る前に一回りし、状況把握できたことは良かった。
☆悪かった点
準備不足。畑の整備をするべきで座る所は確保したい。(後輩に残すもの)立ちっぱなしはしんどいので、ブルーシートを確保する。
→備品の購入が必要。(鋸、ブルーシート)
という感じですが、やはり山菜パーティーがないと春は始まりません。春の幸を噛み締め、ほんのりとした苦みを感じることが何より大切なのではないでしょうか。今年度は、新たな企画を盛り込み、その分準備不足で、多大な迷惑を被った方も多くいたことでしょう。
それでも、相互に助け合うという精神は、社会人に必要な資質の一つであり、一日通して皆さんの能力の高さに感謝ばかりでした。
このサークルは表に出る活動はしていませんが、素晴らしく、未来への提言を含めた面白い企画を盛り込むサークルであると信じています。
今日は、みんなと山菜を食えて良かった。ただそれだけす。
活動場所:ゴルフ場奥の山、畑部会の畑
活動メンバー:1回生5人、2回生1人、3回生8人、4回生1人、OB1人
報告:遂に3回生になった小林
2014年04月08日
コバノミツバツツジ 満開
現在の裏山の様子。
コバノミツバツツジ( Rhododendron reticulatum)が咲き誇っています。
美しいです。この美しさは多くの人と楽しみたいです。
新入生よ集え。と言いたいですが、どうすればいのでしょうか?
色んな楽しいサークルはありますが、校内の自然と触れ合えるサークルは他にないでしょう。
しかし、この声はなかなか届かないのです。かき消されるのです。これが残念な話で、私の生涯の課題であります。
自然へ触れるきっかけ作りができる人間になることを常々心掛けて行きたいものです。
いやあ、結構悔しいですね。
投稿:小林
2014年04月08日
今年度の展望
こんにちは。
お久しぶりの投稿です。
今年度の目標、というか、展望です。
春
山菜取りなど、山の幸をいただく。
また、図鑑作りという目標を持って皆で作り上げるプランを実行する。
夏
カシナガで面白い企画を1つ実行する。
秋
図鑑作り、そして涼しくなれば間伐作業。紅葉狩り。
冬
図鑑作り、間伐作業
という様に活動計画を立てました。
一つ困ったことは、気合いを入れて具体的な活動計画を作ってしまわない限り、あっちへ向いたり、こっちへ向いたりの繰り返しです。
来週会議を行い、考えましょう。
また、今年度のポイントとして私が挙げるとすれば
土地利用の歴史に関する考察をすること、また外部団体の活動に参加することの2点です。
前者は、京田辺で4年間學ぶ者としてこのテーマに首を突っ込む機会は今年しかないため力を入れます。
後者は、やましろ里山の会の活動に参加し、各々の成長に繋げられればと考えています。
正直、今現在、頭の中では色々「やりたいこと」が走り回っていて宜しくない状況です。
一度、原点に立ち返り、この大学で出会った「里山部会」で自分の成長を感じられるよう頑張ろうという決意であります。
最後に1言
先日、裏山の広場にキジのつがいがいました。
大学のゴミ置き場と化している場でもありますが、一つ楽しみが増えました。
また、イタチ(おそらくチョウセンイタチ)もいました。
以上。
投稿:小林
お久しぶりの投稿です。
今年度の目標、というか、展望です。
春
山菜取りなど、山の幸をいただく。
また、図鑑作りという目標を持って皆で作り上げるプランを実行する。
夏
カシナガで面白い企画を1つ実行する。
秋
図鑑作り、そして涼しくなれば間伐作業。紅葉狩り。
冬
図鑑作り、間伐作業
という様に活動計画を立てました。
一つ困ったことは、気合いを入れて具体的な活動計画を作ってしまわない限り、あっちへ向いたり、こっちへ向いたりの繰り返しです。
来週会議を行い、考えましょう。
また、今年度のポイントとして私が挙げるとすれば
土地利用の歴史に関する考察をすること、また外部団体の活動に参加することの2点です。
前者は、京田辺で4年間學ぶ者としてこのテーマに首を突っ込む機会は今年しかないため力を入れます。
後者は、やましろ里山の会の活動に参加し、各々の成長に繋げられればと考えています。
正直、今現在、頭の中では色々「やりたいこと」が走り回っていて宜しくない状況です。
一度、原点に立ち返り、この大学で出会った「里山部会」で自分の成長を感じられるよう頑張ろうという決意であります。
最後に1言
先日、裏山の広場にキジのつがいがいました。
大学のゴミ置き場と化している場でもありますが、一つ楽しみが増えました。
また、イタチ(おそらくチョウセンイタチ)もいました。
以上。
投稿:小林
2014年02月24日
「手入れ」という考え方
今日は、「手入れの思想」という考え方についてです。
私たちは毎日、自宅を出る時は、服装や髪型を整え、帰宅後は風呂に入ります。
部屋は定期的に掃除し、過ごしやすい空間を保っていることでしょう。
これは、「手入れ」を行っているということになります。
山との向き合い方も、以上のような考え方を当たり前にすれば良いのではないでしょうか。
つまり、手入れの思想です。
日本の山をどうするかといった大きな政策等は、国のトップの官僚の決定に委ねられる部分があることは否めません。
官僚はかなりお忙しく、山に出向いて自然の声に耳を傾けるほど生活に余裕がありません。言い換えると、自然と共生しているという実感に乏しい生活をしているといえるでしょう。
そんな方々に政策を委ねてしまっては、どんなことが起きるでしょうか。
想像すると、1つに、理論通りに行うことが正しいという信じて、その通りに政策を打ち出してしまうのではないか、ということが挙げられます。
その理論を構築していくのが、大学・研究機関等の研究データであると考えています。理論は確かに大切です。
ただ、私が20年少し生きて中で、大人はいつもこう言っていたように思います。
「最終的には臨機応変に。」「最後は自分の直観を信じて。」と。
つまり理論通りには物事進まないと大人は経験で分かっていて、私に話をして下さったのでしょう。自然科学系の実験データを解析する際に用いる式1つとっても、あくまでモデルの式であることに異論はなく、必ずや誤差が生じるのです。
理論というのは、一旦構築されると、それ考えなくて良いという勘違いが生じます。そこが危険なのです。
現場で日々自然と向き合う方々は、自然の声に耳を傾けています。私たちも、やはり日々の手入れという視点を持ち、物事に取り組んでいく必要性を感じますね。
このサークルにとって、あまり現実的な考え方ではないと思いますが、手入れするという意識を持つ重要性について書いてみました。
投稿;小林
私たちは毎日、自宅を出る時は、服装や髪型を整え、帰宅後は風呂に入ります。
部屋は定期的に掃除し、過ごしやすい空間を保っていることでしょう。
これは、「手入れ」を行っているということになります。
山との向き合い方も、以上のような考え方を当たり前にすれば良いのではないでしょうか。
つまり、手入れの思想です。
日本の山をどうするかといった大きな政策等は、国のトップの官僚の決定に委ねられる部分があることは否めません。
官僚はかなりお忙しく、山に出向いて自然の声に耳を傾けるほど生活に余裕がありません。言い換えると、自然と共生しているという実感に乏しい生活をしているといえるでしょう。
そんな方々に政策を委ねてしまっては、どんなことが起きるでしょうか。
想像すると、1つに、理論通りに行うことが正しいという信じて、その通りに政策を打ち出してしまうのではないか、ということが挙げられます。
その理論を構築していくのが、大学・研究機関等の研究データであると考えています。理論は確かに大切です。
ただ、私が20年少し生きて中で、大人はいつもこう言っていたように思います。
「最終的には臨機応変に。」「最後は自分の直観を信じて。」と。
つまり理論通りには物事進まないと大人は経験で分かっていて、私に話をして下さったのでしょう。自然科学系の実験データを解析する際に用いる式1つとっても、あくまでモデルの式であることに異論はなく、必ずや誤差が生じるのです。
理論というのは、一旦構築されると、それ考えなくて良いという勘違いが生じます。そこが危険なのです。
現場で日々自然と向き合う方々は、自然の声に耳を傾けています。私たちも、やはり日々の手入れという視点を持ち、物事に取り組んでいく必要性を感じますね。
このサークルにとって、あまり現実的な考え方ではないと思いますが、手入れするという意識を持つ重要性について書いてみました。
投稿;小林