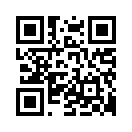2014年02月18日
里山活動という矛盾
☆はじめに☆
こんにちは。本日も教習所から小林です。
(これを書く意図は、後で読み返した時、教習所で本を読んで隙間時間で文章を作っていたぞ!ということを自分に思い出させることです。誠に勝手な話ですが(笑))
今日は、以前も触れた「里山活動に関わる私の矛盾」のお話です。
☆土地を利用することの矛盾☆
始めに言っておきましょう。以下のように、私は自己矛盾を感じておりますが、決して活動自体に後ろめたさを感じているわけではありません。
では、何が矛盾か、まずはそれについて書きます。
私は、前回(昨日2/16)の投稿にて、土地利用の歴史を知ることこそが、活動を行うにあたって重要だという趣旨の内容を書きました。
私も含め、部員には社会に出てからも何かしらの形で自然と直接関わっていただきたいと思っています。
理由としては、環境を学ぶ学生は知識が豊富であるが故に、どうしても美しい言葉を並べて、あたかも自然を分かったような気になってしまいがちだということが挙げられます。特に、私のように都市環境にすっかり慣れ親しんだ人ほど気をつけるべきだと感じます。全ての人がフィールドにも出なければならないという決まりはありませんが、フィールドに意識を持つこともやはりこれからの時代、必要不可欠となるでしょう。
大学内の山であれば、大学の施設課から許可が下りた以上、ある程度好きなように活動を行うということでよいと考えていますが、社会に出てからは(つまり大学外の活動地)特に活動地となる地域の方々の意向を最優先させなくてはなりません。
しかし、この私見には大きな誤りであるのです。以下の引用を通して考えます。
「土地の歴史という点から里山保全の動きをとらえなおしてみると、里山保全を担っている都市住民や大学は、いったん里山を開発した土地の上で自分たちの生活を営み、里山保全を主張するという矛盾を抱えているからである。」(※1)
ここで言いたい矛盾とは、まさに上記の引用文中の「矛盾」のことです。
☆引用に対する解釈☆
まさに上記は私たちの現状を捉えた引用文であると言えます。
ただ、これを言われれば反論する術がないのではないでしょうか。あたかも、教授に論破された時のように。
このような時はどうすればよいのでしょうか。やはり、私たちがこのことを認識することが最も大切なこととなるでしょう。意識の片隅に入れた上で活動するのと、しないのとでは、一見微差のように思えますが、「塵も積もれば山」という諺の如く、微差が大差を生むのではないか(微差力という本も出回っていますね。)、そのような気がします。
里山活動では、参加者がそれぞれ何かしら「理想の里山」のイメージを無意識のうちに描いて活動しています。私の場合は、スプリングエフェメラルの充実し、ゼフィルスが舞うといった景観です。
里山とは、もともと人の手が加えられた人里近くの山のことですが、これだけ里山活動に対して様々な方面から人が集うと、里山に対する解釈は拡大を続けるでしょう。これは、英語が世界規模へと広がるに従って様々な解釈が加えられ、多様化していくことと似ているような気がします。
同じ「山」と名前が与えれるところでも、そこに根付く歴史、先人の気持ちは実に様々で一括りすることは出来ません。里山という言葉に関しても、近年になって勝手に広まった言葉に過ぎず、例えば「里山100選」と名付けられたからといって特にその景観には何も変化はないのです。
お化粧をすれば綺麗に変身する、アクセサリーを付けて髪を染めセットすれば格好良くなるといったように、この世界は装飾であふれています。
ただの山なのに、そこに人の惹き付けられるような「言葉」という飾りつけを行い、価値を与えようとするのが我々人間の性ですから、仕方のないことです。
だから、私たちはそのような言葉、ここでいうなら「里山」という美しい言葉に、惑わされ本質を失わないよう、地域を大切に取り組んでいくべきなのです。
矛盾なんぞ、世の中溢れているのですから。
以上です。
(※1:里山学のまなざし 丸山徳氏、宮浦富保編 昭和堂 2009 初版 p.143)
投稿:小林
こんにちは。本日も教習所から小林です。
(これを書く意図は、後で読み返した時、教習所で本を読んで隙間時間で文章を作っていたぞ!ということを自分に思い出させることです。誠に勝手な話ですが(笑))
今日は、以前も触れた「里山活動に関わる私の矛盾」のお話です。
☆土地を利用することの矛盾☆
始めに言っておきましょう。以下のように、私は自己矛盾を感じておりますが、決して活動自体に後ろめたさを感じているわけではありません。
では、何が矛盾か、まずはそれについて書きます。
私は、前回(昨日2/16)の投稿にて、土地利用の歴史を知ることこそが、活動を行うにあたって重要だという趣旨の内容を書きました。
私も含め、部員には社会に出てからも何かしらの形で自然と直接関わっていただきたいと思っています。
理由としては、環境を学ぶ学生は知識が豊富であるが故に、どうしても美しい言葉を並べて、あたかも自然を分かったような気になってしまいがちだということが挙げられます。特に、私のように都市環境にすっかり慣れ親しんだ人ほど気をつけるべきだと感じます。全ての人がフィールドにも出なければならないという決まりはありませんが、フィールドに意識を持つこともやはりこれからの時代、必要不可欠となるでしょう。
大学内の山であれば、大学の施設課から許可が下りた以上、ある程度好きなように活動を行うということでよいと考えていますが、社会に出てからは(つまり大学外の活動地)特に活動地となる地域の方々の意向を最優先させなくてはなりません。
しかし、この私見には大きな誤りであるのです。以下の引用を通して考えます。
「土地の歴史という点から里山保全の動きをとらえなおしてみると、里山保全を担っている都市住民や大学は、いったん里山を開発した土地の上で自分たちの生活を営み、里山保全を主張するという矛盾を抱えているからである。」(※1)
ここで言いたい矛盾とは、まさに上記の引用文中の「矛盾」のことです。
☆引用に対する解釈☆
まさに上記は私たちの現状を捉えた引用文であると言えます。
ただ、これを言われれば反論する術がないのではないでしょうか。あたかも、教授に論破された時のように。
このような時はどうすればよいのでしょうか。やはり、私たちがこのことを認識することが最も大切なこととなるでしょう。意識の片隅に入れた上で活動するのと、しないのとでは、一見微差のように思えますが、「塵も積もれば山」という諺の如く、微差が大差を生むのではないか(微差力という本も出回っていますね。)、そのような気がします。
里山活動では、参加者がそれぞれ何かしら「理想の里山」のイメージを無意識のうちに描いて活動しています。私の場合は、スプリングエフェメラルの充実し、ゼフィルスが舞うといった景観です。
里山とは、もともと人の手が加えられた人里近くの山のことですが、これだけ里山活動に対して様々な方面から人が集うと、里山に対する解釈は拡大を続けるでしょう。これは、英語が世界規模へと広がるに従って様々な解釈が加えられ、多様化していくことと似ているような気がします。
同じ「山」と名前が与えれるところでも、そこに根付く歴史、先人の気持ちは実に様々で一括りすることは出来ません。里山という言葉に関しても、近年になって勝手に広まった言葉に過ぎず、例えば「里山100選」と名付けられたからといって特にその景観には何も変化はないのです。
お化粧をすれば綺麗に変身する、アクセサリーを付けて髪を染めセットすれば格好良くなるといったように、この世界は装飾であふれています。
ただの山なのに、そこに人の惹き付けられるような「言葉」という飾りつけを行い、価値を与えようとするのが我々人間の性ですから、仕方のないことです。
だから、私たちはそのような言葉、ここでいうなら「里山」という美しい言葉に、惑わされ本質を失わないよう、地域を大切に取り組んでいくべきなのです。
矛盾なんぞ、世の中溢れているのですから。
以上です。
(※1:里山学のまなざし 丸山徳氏、宮浦富保編 昭和堂 2009 初版 p.143)
投稿:小林
2014年02月17日
竹みつまたプロジェクト
こんばんは。
そしてブログお久しぶりなのか初めてなのか忘れましたが、もうすぐ追い出される4回の津田です(笑)
2月15日(土)に大学の近く(もはやKEの丁度下辺り)のビオ多々羅という場所で竹みつまたプロジェクトのイベントがありました!
これは竹フェスタというイベントと連携したイベントです。
ちなみに僕が里山部会長だった時にe-cycleとしてきゅうたなべ倶楽部と共催という形で竹フェスタを開催しました。
といっても2年前の話ですが…笑
放置竹林という問題を解決すべく、まずは皆に知ってもらおう+地域活性化というイベントです。
実は去年もやってました(報告してませんが…笑)
とりあえず話を元に戻します(笑)
この竹みつまたプロジェクトは鹿が嫌うみつまたを植えることで竹林の拡大を防ぐかもしれないという例を実証するプロジェクトで去年の2月は木津川市の鹿背山で竹林にみつまたの植樹を行いました!(これも報告してません、すみませんm(_ _)m笑)
今年は様々な学生団体(国際ボランティア団体IVUSA、生物同好会、きゅうたなべ倶楽部など)と京田辺市社会福祉協議会、ビオ多々羅などの団体と協力してビオ多々羅で行いました!
当日は前日の積雪が残っている中、篠笛作成体験、竹林の周辺にミツマタの植樹、昼ごはんに無農薬野菜のカレーなど盛り沢山で地域の高齢者の方や子どもたちが参加し、学生はスタッフという形でした。
ちなみにe-cycleからは僕含め3人で参加しました!
植樹したミツマタはこんな木です。

本当は三つに分かれてるはずですが、これだけ4つに分かれてました(笑)
ミツマタは低木なので、最終的にそんなに大きくはなりません。
そして植樹の風景です。

ザブが植えてます(笑)
ちなみに僕は雪で靴がぐちゃぐちゃで植える気になりませんでした(笑)←
昼飯は無農薬野菜のカレーと風呂吹き大根でした!

めっちゃ美味かったです^^
そして最後に参加者の方々とスタッフで集合写真を撮りました!

参加者の方々、ありがとうございました(^^)/
一昨年の竹フェスタ、去年2月の竹みつまたプロジェクト、10月の竹フェスタと続き、今回の竹みつまたプロジェクトで僕はこの担当から下ります。
今年、来年以降やるかどうかは後輩に判断を委ねます!
今まで本当にありがとうございましたm(_ _)m
報告:元里山部会長兼広報担当、現里山部会顧問 4年 津田
そしてブログお久しぶりなのか初めてなのか忘れましたが、もうすぐ追い出される4回の津田です(笑)
2月15日(土)に大学の近く(もはやKEの丁度下辺り)のビオ多々羅という場所で竹みつまたプロジェクトのイベントがありました!
これは竹フェスタというイベントと連携したイベントです。
ちなみに僕が里山部会長だった時にe-cycleとしてきゅうたなべ倶楽部と共催という形で竹フェスタを開催しました。
といっても2年前の話ですが…笑
放置竹林という問題を解決すべく、まずは皆に知ってもらおう+地域活性化というイベントです。
実は去年もやってました(報告してませんが…笑)
とりあえず話を元に戻します(笑)
この竹みつまたプロジェクトは鹿が嫌うみつまたを植えることで竹林の拡大を防ぐかもしれないという例を実証するプロジェクトで去年の2月は木津川市の鹿背山で竹林にみつまたの植樹を行いました!(これも報告してません、すみませんm(_ _)m笑)
今年は様々な学生団体(国際ボランティア団体IVUSA、生物同好会、きゅうたなべ倶楽部など)と京田辺市社会福祉協議会、ビオ多々羅などの団体と協力してビオ多々羅で行いました!
当日は前日の積雪が残っている中、篠笛作成体験、竹林の周辺にミツマタの植樹、昼ごはんに無農薬野菜のカレーなど盛り沢山で地域の高齢者の方や子どもたちが参加し、学生はスタッフという形でした。
ちなみにe-cycleからは僕含め3人で参加しました!
植樹したミツマタはこんな木です。
本当は三つに分かれてるはずですが、これだけ4つに分かれてました(笑)
ミツマタは低木なので、最終的にそんなに大きくはなりません。
そして植樹の風景です。
ザブが植えてます(笑)
ちなみに僕は雪で靴がぐちゃぐちゃで植える気になりませんでした(笑)←
昼飯は無農薬野菜のカレーと風呂吹き大根でした!
めっちゃ美味かったです^^
そして最後に参加者の方々とスタッフで集合写真を撮りました!

参加者の方々、ありがとうございました(^^)/
一昨年の竹フェスタ、去年2月の竹みつまたプロジェクト、10月の竹フェスタと続き、今回の竹みつまたプロジェクトで僕はこの担当から下ります。
今年、来年以降やるかどうかは後輩に判断を委ねます!
今まで本当にありがとうございましたm(_ _)m
報告:元里山部会長兼広報担当、現里山部会顧問 4年 津田
2014年02月16日
土地利用の歴史を知ろう
☆はじめに☆
こんにちは。教習所の喫茶店から小林です。
大学に入ってから思うことで、文章は書けば書くほど、その力は上達するものです。しかし、私はその機会に乏しい。
同大ではなく、猛者の集う他大学のサークルの一員でもある私にとって、得ようと思えばいくらでも文章を書く機会は得られるのですが、なかなか踏み出せません。いけませんね。
ちなみに、私の務めている塾にはテーマソングが存在し、その名は「踏み出して♪」です。聞くたびに心に響きます。
従って、来年度は忙しい時でも自分に少し厳しくなり、文章を書こうと思う次第であります。
さてさて、今日は土地利用の話です。
☆「里山活動」の現状☆
もともと江戸時代から使われ始めたとされる「里山」という言葉ですが、私の大学の教授の恩師である四手井氏によって、高度経済成長期を経て、再定義され、脚光を浴びるようになったと言われています。今では、satoyama という横文字が出来ているほどです。
そして現在、里山活動は全国的に一種ブームのようになっています。活動団体は1000を遥かに超えるていると思います。
それぞれの団体には、活動目的・意義があるでしょう。どれも素敵な活動であることに異論はありません。
一方で、「里山か。ただのブームだ。うさんくさい。」と感じている方々(特に専門家)もいらっしゃるように感じます。
以前、とある学会の公聴会に参加したときのこと。今以上に経験に乏しかった私が、自分の行っている活動についてアドバイスを求める質問を会場でした時、会場が静まり返るのを肌で感じました。学問として「里山」と触れている方々の厳しい視線を感じた思いでした。(実際どうかはわかりませんが。)
実際、地球温暖化でCO2排出減少を唄い会社の宣伝にしていると同様、補助金を得る手段として里山活動をする会社も多いという現状があるように思います。「美しい日本の景観を残していこう」といった美しい文言を残す所までは立派なものの、実質が伴っていないということでしょう。
☆学生団体としての里山活動☆
そんな現状を踏まえ、私たちが京田辺キャンパスで里山活動を行うにあたって大切なのは、京田辺の過去の土地利用の歴史を知ることです。
先輩方が細々と受け継いでこられたこの里山部会は、意外にも、土地利用について調べられてこなかったようです。次なるステップへ進むためには、まず基本に立ち返る必要があるでしょう。
木を伐ることなどの行為や汗を流して活動すること自体に意味はあり、そこから個々人が感じること学ぶことは多くありますが、やはり、過去の京田辺を知らなければただのお遊びの活動になり兼ねません。
そこで、活動と並行した形になりますが、今、私たちは土地利用の歴史を知る段階に差し掛かろうとしています。
コンクリで覆われる現在において、実感として乏しいかもしれないが、毎日踏んでいるこの土には、地域の歴史が根付いています。その「地面に根付く歴史」を知ろうと思います。
☆土地利用を知るための手段☆
基本的には、方法は2つあると考えています。1つは、過去の文献の記載・研究等による植生調査の結果から土地利用のヒントを得ること。2つ目は、地元の方々からお話を伺うことです。
1つ目は比較的忙しい年末に行おうと思いました。用いたのは、「同志社田辺校地の植生と植物相 : 特に植生と土壌および地質との関連性について」(同志社大学校地学術調査委員会、1984)です。今、手元に資料がないため、この場で、講評を行うことは出来ませんので別の機会に致します。
2つ目は単純に地元の方々からお話を伺うきわめてシンプルな方法です。ここでポイントとなるのが、コミュニケーション能力であると言えます。e-cycleでは今年度新たにエココミュニケーション部会(通称、エコミュ部会)ができ、自分たちの考え方を他者に伝える際に大切となるコミュニケーションの取り方について、プレゼン・スピーチの方法等を部員が相互に学び合いスキルを高めたりと、興味深い活動を行っています。
私たち里山部会も、エコミュ部会の考え方を参考に、地元の方々と質の高いコミュニケーションを取ろうと思います。(おそらくは私がほとんど行う?)
具体的にですが、最近個人的にコンタクトが取れているNPO団体「やましろ里山の会」の方々から地域の歴史を伺おうと思います。そのご報告はまたの機会にしようと思います。
☆最後に☆
この部会は、言うまでもなく指導者がいない状況です。私は、思い返せば高校の時、とある運動部の部長を努めていた際、毎日の練習メニューは過去の先輩の見よう見真似で同期と考えていたことを思い出します。現状もそれと似た感じがします。
指図されて動くより、自分の考えたことを実行する方が楽しいと思う性格が活かされますね。(笑)
だからこそ、教授が先頭を切って活動している諸大学には何かしら張り合いたい気持ちが強くあります。
土地利用の歴史を知ることで、まずは大学の裏山に対する興味関心が深まり、また、私たちの活動の指針を作ってくれることでしょう。
早めに動いて次に繋がる成果をご報告できるといいですね。今日のところはここまで。
投稿:理工学部環境システム学科B2 小林
こんにちは。教習所の喫茶店から小林です。
大学に入ってから思うことで、文章は書けば書くほど、その力は上達するものです。しかし、私はその機会に乏しい。
同大ではなく、猛者の集う他大学のサークルの一員でもある私にとって、得ようと思えばいくらでも文章を書く機会は得られるのですが、なかなか踏み出せません。いけませんね。
ちなみに、私の務めている塾にはテーマソングが存在し、その名は「踏み出して♪」です。聞くたびに心に響きます。
従って、来年度は忙しい時でも自分に少し厳しくなり、文章を書こうと思う次第であります。
さてさて、今日は土地利用の話です。
☆「里山活動」の現状☆
もともと江戸時代から使われ始めたとされる「里山」という言葉ですが、私の大学の教授の恩師である四手井氏によって、高度経済成長期を経て、再定義され、脚光を浴びるようになったと言われています。今では、satoyama という横文字が出来ているほどです。
そして現在、里山活動は全国的に一種ブームのようになっています。活動団体は1000を遥かに超えるていると思います。
それぞれの団体には、活動目的・意義があるでしょう。どれも素敵な活動であることに異論はありません。
一方で、「里山か。ただのブームだ。うさんくさい。」と感じている方々(特に専門家)もいらっしゃるように感じます。
以前、とある学会の公聴会に参加したときのこと。今以上に経験に乏しかった私が、自分の行っている活動についてアドバイスを求める質問を会場でした時、会場が静まり返るのを肌で感じました。学問として「里山」と触れている方々の厳しい視線を感じた思いでした。(実際どうかはわかりませんが。)
実際、地球温暖化でCO2排出減少を唄い会社の宣伝にしていると同様、補助金を得る手段として里山活動をする会社も多いという現状があるように思います。「美しい日本の景観を残していこう」といった美しい文言を残す所までは立派なものの、実質が伴っていないということでしょう。
☆学生団体としての里山活動☆
そんな現状を踏まえ、私たちが京田辺キャンパスで里山活動を行うにあたって大切なのは、京田辺の過去の土地利用の歴史を知ることです。
先輩方が細々と受け継いでこられたこの里山部会は、意外にも、土地利用について調べられてこなかったようです。次なるステップへ進むためには、まず基本に立ち返る必要があるでしょう。
木を伐ることなどの行為や汗を流して活動すること自体に意味はあり、そこから個々人が感じること学ぶことは多くありますが、やはり、過去の京田辺を知らなければただのお遊びの活動になり兼ねません。
そこで、活動と並行した形になりますが、今、私たちは土地利用の歴史を知る段階に差し掛かろうとしています。
コンクリで覆われる現在において、実感として乏しいかもしれないが、毎日踏んでいるこの土には、地域の歴史が根付いています。その「地面に根付く歴史」を知ろうと思います。
☆土地利用を知るための手段☆
基本的には、方法は2つあると考えています。1つは、過去の文献の記載・研究等による植生調査の結果から土地利用のヒントを得ること。2つ目は、地元の方々からお話を伺うことです。
1つ目は比較的忙しい年末に行おうと思いました。用いたのは、「同志社田辺校地の植生と植物相 : 特に植生と土壌および地質との関連性について」(同志社大学校地学術調査委員会、1984)です。今、手元に資料がないため、この場で、講評を行うことは出来ませんので別の機会に致します。
2つ目は単純に地元の方々からお話を伺うきわめてシンプルな方法です。ここでポイントとなるのが、コミュニケーション能力であると言えます。e-cycleでは今年度新たにエココミュニケーション部会(通称、エコミュ部会)ができ、自分たちの考え方を他者に伝える際に大切となるコミュニケーションの取り方について、プレゼン・スピーチの方法等を部員が相互に学び合いスキルを高めたりと、興味深い活動を行っています。
私たち里山部会も、エコミュ部会の考え方を参考に、地元の方々と質の高いコミュニケーションを取ろうと思います。(おそらくは私がほとんど行う?)
具体的にですが、最近個人的にコンタクトが取れているNPO団体「やましろ里山の会」の方々から地域の歴史を伺おうと思います。そのご報告はまたの機会にしようと思います。
☆最後に☆
この部会は、言うまでもなく指導者がいない状況です。私は、思い返せば高校の時、とある運動部の部長を努めていた際、毎日の練習メニューは過去の先輩の見よう見真似で同期と考えていたことを思い出します。現状もそれと似た感じがします。
指図されて動くより、自分の考えたことを実行する方が楽しいと思う性格が活かされますね。(笑)
だからこそ、教授が先頭を切って活動している諸大学には何かしら張り合いたい気持ちが強くあります。
土地利用の歴史を知ることで、まずは大学の裏山に対する興味関心が深まり、また、私たちの活動の指針を作ってくれることでしょう。
早めに動いて次に繋がる成果をご報告できるといいですね。今日のところはここまで。
投稿:理工学部環境システム学科B2 小林
2014年02月14日
間伐作業 〜極寒の中で〜
久しぶりの更新となります。
本日は活動日でした。
エリア設定・植生調査を踏まえた今、行うべきことは理想の形を考え、イメージを共有することです。
同志社大学京田辺キャンパスの裏山の中で、今のエリアを選んだ根拠として、「コナラ優占林の中に竹が侵入しているエリアであること」が挙げられます。
果たしてコナラ優占林とモウソウチク・ハチク林の共存は可能なのでしょうか。
今後、整備を踏まえた上で実験をしていこうと考えています。
理想の形は、コナラをシンボルツリーとした優占林とすることでしょう。
エリア内には、京都府でも比較的珍しいコクランが見られます。
この種はラン科の中でも光合成を行う種であるため、菌根類との共生関係にあるものではないということです。
また、エリアの端である尾根筋には、コバミツやモチツツジが生えており、初夏に花が楽しめます。
という訳で、本日は鬱蒼としているハチク、株立ちのソヨゴ、ヒサカキの間伐を行いました。
間伐の途中で伐らざるを得なくなったコナラは、何と樹齢30年近くのものでした。
受け皿を作りノコギリで「ギコギコギコ。。」
「メシッ!!」と生きた木の音が鳴り響き、怪我なく倒すことが出来ました。
今日は気温が5℃ほどであり、霰も降り、寒かったですね。
箒作りが残りました。今度、続きをしましょう!!
ハチクは畑まで運びました。(重かったな笑)
一日通して凄くいい運動となりました。明日は筋肉痛!?明日になってみないとわかりませんね。
活動時間:11:00〜13:30
活動人数:5人(2回生)
報告:理工学部環境システム学科 小林
本日は活動日でした。
エリア設定・植生調査を踏まえた今、行うべきことは理想の形を考え、イメージを共有することです。
同志社大学京田辺キャンパスの裏山の中で、今のエリアを選んだ根拠として、「コナラ優占林の中に竹が侵入しているエリアであること」が挙げられます。
果たしてコナラ優占林とモウソウチク・ハチク林の共存は可能なのでしょうか。
今後、整備を踏まえた上で実験をしていこうと考えています。
理想の形は、コナラをシンボルツリーとした優占林とすることでしょう。
エリア内には、京都府でも比較的珍しいコクランが見られます。
この種はラン科の中でも光合成を行う種であるため、菌根類との共生関係にあるものではないということです。
また、エリアの端である尾根筋には、コバミツやモチツツジが生えており、初夏に花が楽しめます。
という訳で、本日は鬱蒼としているハチク、株立ちのソヨゴ、ヒサカキの間伐を行いました。
間伐の途中で伐らざるを得なくなったコナラは、何と樹齢30年近くのものでした。
受け皿を作りノコギリで「ギコギコギコ。。」
「メシッ!!」と生きた木の音が鳴り響き、怪我なく倒すことが出来ました。
今日は気温が5℃ほどであり、霰も降り、寒かったですね。
箒作りが残りました。今度、続きをしましょう!!
ハチクは畑まで運びました。(重かったな笑)
一日通して凄くいい運動となりました。明日は筋肉痛!?明日になってみないとわかりませんね。
活動時間:11:00〜13:30
活動人数:5人(2回生)
報告:理工学部環境システム学科 小林
2013年12月08日
活動内容に頭がいっぱいの私
こんばんは。
ふと思ったので書き残したいと思います。
私たちは、同志社大学京田辺校地に残る自然を活動地とさせていただいています。
本来はそれだけでもありがたい話なのですが、活動内容を楽しくしよう!ということばかりを意識するがあまり心から自然と向き合えていない自分がいることに気づかされます。
確かに、まだ世の中で試したことがないことを初めて行うというのはワクワクして心躍るものです。
ただ忘れてはならないこと、それは「活動内容そのものは目的ではなくあくまで手段である」ということです。
ips細胞をはじめ世間から喝采を受けている物も、あれ自体の発見が人類の最終目的なのではなく、目的を果たす為の一手段に過ぎません。(その目的とはなんなのでしょうか。私にはまだ答えが出せずにいます。)
この部会の活動目的は、「生態系の中で里山という概念が用いられる自然はどのような位置づけにあるのか、活動を通して感じ、同時に学ぶこと」でしょう。
その目的を果たそうという努力の過程において、ワクワクする活動内容があることになります。
このままでは、「生物多様性」や「人と自然の共生」など、ただきれいごとを並べている人になってしまうのではないか。そんな風に思ってしまいます。
言葉は難しく、「土地利用」という言葉でさえ見方によれば「人優位」の捉え方になってしまいます。
私たちはもっと謙虚に自然に学ばせていただくという気持ちで里山部会の活動を行っていくべきでしょう。
「今日も宜しくお願いします!」これくらいの姿勢は忘れてはいけませんね。
自然からの恩恵を実生活で感じる機会が少なくなっている近年、心から自然を敬うと同時に畏れる気持ちというのは薄いのではないでしょうか。
従ってこのようなことを考えることに意味はあるでしょう。
これは私自身の人生にも言えることで、日々学ばせていただいていることばかり、その当たり前のことに対して感謝していく必要があるでしょう。
投稿:小林
ふと思ったので書き残したいと思います。
私たちは、同志社大学京田辺校地に残る自然を活動地とさせていただいています。
本来はそれだけでもありがたい話なのですが、活動内容を楽しくしよう!ということばかりを意識するがあまり心から自然と向き合えていない自分がいることに気づかされます。
確かに、まだ世の中で試したことがないことを初めて行うというのはワクワクして心躍るものです。
ただ忘れてはならないこと、それは「活動内容そのものは目的ではなくあくまで手段である」ということです。
ips細胞をはじめ世間から喝采を受けている物も、あれ自体の発見が人類の最終目的なのではなく、目的を果たす為の一手段に過ぎません。(その目的とはなんなのでしょうか。私にはまだ答えが出せずにいます。)
この部会の活動目的は、「生態系の中で里山という概念が用いられる自然はどのような位置づけにあるのか、活動を通して感じ、同時に学ぶこと」でしょう。
その目的を果たそうという努力の過程において、ワクワクする活動内容があることになります。
このままでは、「生物多様性」や「人と自然の共生」など、ただきれいごとを並べている人になってしまうのではないか。そんな風に思ってしまいます。
言葉は難しく、「土地利用」という言葉でさえ見方によれば「人優位」の捉え方になってしまいます。
私たちはもっと謙虚に自然に学ばせていただくという気持ちで里山部会の活動を行っていくべきでしょう。
「今日も宜しくお願いします!」これくらいの姿勢は忘れてはいけませんね。
自然からの恩恵を実生活で感じる機会が少なくなっている近年、心から自然を敬うと同時に畏れる気持ちというのは薄いのではないでしょうか。
従ってこのようなことを考えることに意味はあるでしょう。
これは私自身の人生にも言えることで、日々学ばせていただいていることばかり、その当たり前のことに対して感謝していく必要があるでしょう。
投稿:小林