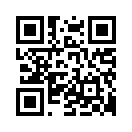2013年10月02日
10月2日の記事
こんばんは、更新率をあげるという様に書いていましたが、忘れてしまっていました。
まあ許してあげましょう!!
まずは、同志社大学京田辺キャンパスの裏山の近況、そして、その後に日本の森林について書きます。
☆近況
ナラ枯れによって枯死したコナラ(Quercus serrata)の個体数に関して正確には勘定していませんが、7月に予想していよりは枯死していない印象を受けます。つまり、最悪の事態は耐えたということでしょう。
ところで、少しびっくりする事が起きています。大学の関係者がして下さったであろうと推測していますが、コナラ枯死個体が一本伐採されていました。
学生だけではチェーンソーを使うのは危険ですし、カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)のマスアタックを受けて弱って枯れた(順序は逆かもしれませんが)ことは事実ですので、被害拡大を防ぐ為にも伐採して頂き本当にありがたい話です。
ただ、伐ったコナラを放ったらかしというのは正直疑問です。おそらく我々に後始末をしてもらおうという考えであると思いますが、ナラ枯れに関して正しい知識を持っている場合、伐採後にただちに燻蒸するという後始末までするのが自然な流れです。伐採する事で、突然倒れるという危険性は免れる事になりますが。
実際、間伐時を含めた伐採後の丸太がカシナガの拠点になるという研究例もあるくらいですから、処理方法には気を払った方が良いと考えます。
したがって、里山部会として行って行くべきことは、まず後始末をする事であると思います。
山の中は蚊が多く、スズメバチの仲間が徐々に増えてきた印象を受けます。先日、2時間山にいたため顔が晴れ上がるほど刺されたので正直なところ暫くは入りたくないですね(笑)
☆日本の森林
最近久々に本を読みました。研究室においてあった現代日本生物誌6「マツとシイ」という原田さん執筆の本です。
自分なりにまとめてみます。
日本の山は縄文時代から基本的には人が関わりをもってきたため、約50年前の燃料革命以降生活スタイルが急激に変化しました。
山からの恩恵を受けなくても生きていけるわけですから、手間のかかる山仕事をする人は当然減る訳です。
この本では、一般的に遷移という点で対極にある2つの樹木に関してそれぞれの性質を述べ、絵画や書物や写真を通して植生の変化があるということを述べています。登場人物のマツは土壌が肥沃でない場所でも生育する樹木です。
もう一方のシイは、少なくとも西日本では極相林であり、実は枝を伸ばす事においては他の照葉樹よりも長けているという点でパイオニア的性質も兼ね備えています。
もともとマツが多かった地域が、人が手を加えなくなった事で徐々に照葉樹林に変化していく様を写真を通して記述しており、新鮮な印象を受けました。
これからの日本の森林をどのようにしていくか考えるにあたって、やはり地域地域の取り組みが重要になってくると思います。
というのも、本書でも取り上げられていますが、地域によってこれまでの先人の森林の利用方が異なるからです。その歴史を学び、どうしていくのが現時点でベストな選択であるか考える必要があるのでしょう。
地域毎で考えて行く事になると、地域の繋がりが自ずと生まれます。核家族化が進んだことで地域の繋がりが薄くなっているといわれる現代において、地域の繋がりを取り戻すという意味を踏まえると地域単位で住民参画型の森林活動を行う意義はあります。
自分も地元の里山活動に参加することがありますが、毎回おじさんおばさんから積年の技を教えてもらえます。書物ではなく身振り手振りを交えて上の世代から受け継いだ技というのはまさに「遺産」となります。
中には口うるさい方もいらっしゃいます。そうやって色んな人生経験を持った人とふれあう機会を青年期までに得ているのと得ていないのでは社会に出たときに大きな差が生じる気がしています。
しかし、ただ単に活動すればいいという話ではありません。過去を学ぶ際には過去の文献や複数人に対して聞き取り調査、古写真などを利用します。この際、学術的に一連の資料から分析できる論文が書けるような人材が必要になります。
つまりどういうことかと言うと、地域の中でもピラミッド構造が成立している必要があるということです。アマチュアの自然に詳しい人と、専門家たるひとは区別できなければいけません。また、活動を継続して行くに際しては地域の盛り上げ役なる人の存在も必要ですし、色んな経歴を持つ人が気軽に参画できるコミュニティが必要になってきます。これらのコミュニティのなかで健全な(定義はあいまい)キャッチボールが行われるのが望ましい理想型だと考えます。
そして、地域の中でもどこをどうしてしていくのか共通理解をして活動していくべきでしょう。具体的には、ここは遷移に任せて鬱蒼とした照葉樹林にし、別の場所はマツ林を管理して行く、またある場所はツツジの花道をつくるなど。防災に力をいれるところであればある程度人が管理して行くことが必要となります。共通理解を得るには、やはり学校教育の中で森林に関する正しい知識は教えて行くべきであるでしょう。
遷移を進め自然植生に戻すべきなのか、遷移を食い止めクヌギなど落葉広葉樹林を残してこどもたちの昆虫採集の場所とするのか、何が正しいといのはありません。
正しいという”モデル”はありませんが、前にも書いているように、じっくりとその地域の歴史を振り返り考えて行く事が大切になってくると思います。
どうでしょうか。うまく話がまとまりませんが、日本の森林のあり方について少しは僕自身の中で光が見えてきたような気がしています。やはり書物を読み、色んな人に話を聞き、自分で考えることが重要なのですね。
以上です。
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
まあ許してあげましょう!!
まずは、同志社大学京田辺キャンパスの裏山の近況、そして、その後に日本の森林について書きます。
☆近況
ナラ枯れによって枯死したコナラ(Quercus serrata)の個体数に関して正確には勘定していませんが、7月に予想していよりは枯死していない印象を受けます。つまり、最悪の事態は耐えたということでしょう。
ところで、少しびっくりする事が起きています。大学の関係者がして下さったであろうと推測していますが、コナラ枯死個体が一本伐採されていました。
学生だけではチェーンソーを使うのは危険ですし、カシノナガキクイムシ(以下、カシナガ)のマスアタックを受けて弱って枯れた(順序は逆かもしれませんが)ことは事実ですので、被害拡大を防ぐ為にも伐採して頂き本当にありがたい話です。
ただ、伐ったコナラを放ったらかしというのは正直疑問です。おそらく我々に後始末をしてもらおうという考えであると思いますが、ナラ枯れに関して正しい知識を持っている場合、伐採後にただちに燻蒸するという後始末までするのが自然な流れです。伐採する事で、突然倒れるという危険性は免れる事になりますが。
実際、間伐時を含めた伐採後の丸太がカシナガの拠点になるという研究例もあるくらいですから、処理方法には気を払った方が良いと考えます。
したがって、里山部会として行って行くべきことは、まず後始末をする事であると思います。
山の中は蚊が多く、スズメバチの仲間が徐々に増えてきた印象を受けます。先日、2時間山にいたため顔が晴れ上がるほど刺されたので正直なところ暫くは入りたくないですね(笑)
☆日本の森林
最近久々に本を読みました。研究室においてあった現代日本生物誌6「マツとシイ」という原田さん執筆の本です。
自分なりにまとめてみます。
日本の山は縄文時代から基本的には人が関わりをもってきたため、約50年前の燃料革命以降生活スタイルが急激に変化しました。
山からの恩恵を受けなくても生きていけるわけですから、手間のかかる山仕事をする人は当然減る訳です。
この本では、一般的に遷移という点で対極にある2つの樹木に関してそれぞれの性質を述べ、絵画や書物や写真を通して植生の変化があるということを述べています。登場人物のマツは土壌が肥沃でない場所でも生育する樹木です。
もう一方のシイは、少なくとも西日本では極相林であり、実は枝を伸ばす事においては他の照葉樹よりも長けているという点でパイオニア的性質も兼ね備えています。
もともとマツが多かった地域が、人が手を加えなくなった事で徐々に照葉樹林に変化していく様を写真を通して記述しており、新鮮な印象を受けました。
これからの日本の森林をどのようにしていくか考えるにあたって、やはり地域地域の取り組みが重要になってくると思います。
というのも、本書でも取り上げられていますが、地域によってこれまでの先人の森林の利用方が異なるからです。その歴史を学び、どうしていくのが現時点でベストな選択であるか考える必要があるのでしょう。
地域毎で考えて行く事になると、地域の繋がりが自ずと生まれます。核家族化が進んだことで地域の繋がりが薄くなっているといわれる現代において、地域の繋がりを取り戻すという意味を踏まえると地域単位で住民参画型の森林活動を行う意義はあります。
自分も地元の里山活動に参加することがありますが、毎回おじさんおばさんから積年の技を教えてもらえます。書物ではなく身振り手振りを交えて上の世代から受け継いだ技というのはまさに「遺産」となります。
中には口うるさい方もいらっしゃいます。そうやって色んな人生経験を持った人とふれあう機会を青年期までに得ているのと得ていないのでは社会に出たときに大きな差が生じる気がしています。
しかし、ただ単に活動すればいいという話ではありません。過去を学ぶ際には過去の文献や複数人に対して聞き取り調査、古写真などを利用します。この際、学術的に一連の資料から分析できる論文が書けるような人材が必要になります。
つまりどういうことかと言うと、地域の中でもピラミッド構造が成立している必要があるということです。アマチュアの自然に詳しい人と、専門家たるひとは区別できなければいけません。また、活動を継続して行くに際しては地域の盛り上げ役なる人の存在も必要ですし、色んな経歴を持つ人が気軽に参画できるコミュニティが必要になってきます。これらのコミュニティのなかで健全な(定義はあいまい)キャッチボールが行われるのが望ましい理想型だと考えます。
そして、地域の中でもどこをどうしてしていくのか共通理解をして活動していくべきでしょう。具体的には、ここは遷移に任せて鬱蒼とした照葉樹林にし、別の場所はマツ林を管理して行く、またある場所はツツジの花道をつくるなど。防災に力をいれるところであればある程度人が管理して行くことが必要となります。共通理解を得るには、やはり学校教育の中で森林に関する正しい知識は教えて行くべきであるでしょう。
遷移を進め自然植生に戻すべきなのか、遷移を食い止めクヌギなど落葉広葉樹林を残してこどもたちの昆虫採集の場所とするのか、何が正しいといのはありません。
正しいという”モデル”はありませんが、前にも書いているように、じっくりとその地域の歴史を振り返り考えて行く事が大切になってくると思います。
どうでしょうか。うまく話がまとまりませんが、日本の森林のあり方について少しは僕自身の中で光が見えてきたような気がしています。やはり書物を読み、色んな人に話を聞き、自分で考えることが重要なのですね。
以上です。
同志社大学理工学部環境システム学科
小林慧人
2013年10月01日
夏休みの行事まとめて!!
みなさんお久しぶりです。二宮です。
夏休み後半、更新サボってごめんなさい。
ずぼらで申し訳ないですが、夏休みのイベントまとめて報告します!!
畑部会や里山部会、個人活動等、私が把握していないものもあると思うので、
各自で報告よろしくお願いしますm(_ _)m
08.08
「同志社山手子供会理科教室」
主催:課外活動専門ジブリ会 森先輩と二宮
協力:同志社山手子供会のみなさま
内容:葉脈標本制作、キャンパスツアー
場所:同志社大学京田辺キャンパス
打ち上げ:なし
ブログ:更新済
議事録:更新済(参考資料として、スタッフマニュアルと企画書もあげておきました。)
写真:facebook済
08.11
「ビアガーデン」
主催:3回生
協力:2回生と1回生
内容:飲み会
場所:京都駅の某所
ブログ:自重
写真:いろいろおもしろいの撮れたけど自重
08.20
「滋賀県立大学vs同志社大学サッカー大会」
主催:高村とゆかいな仲間たち
協力:がちすか!で知り合った滋賀県立大学のみなさま
内容:サッカー大会という名の交流会
場所:同志社大学多々羅キャンパス
打ち上げ:焼肉武蔵
ブログ:二宮が怠慢ごめんなさい
議事録:更新済
写真:facebook済
08.23
「親子で環境教育」
主催:環境教育部会 吉永
協力:わがまち京たなべを美しくする会
内容:リサイクル工作、環境クイズラリー
場所:同志社大学京田辺キャンパス
打ち上げ:ルイジアナママ
ブログ:更新済
議事録:更新済(ゆきみちゃんありがとう!)
写真:facebook済
09.08
「京田辺子ども居場所作り 草木染&野菜カルタ」
主催:ジブリ会 森先輩&二宮
協力:京田辺子ども居場所作りのみなさま
内容:たまねぎを使った草木染&野菜カルタ
場所:京田辺区民館
打ち上げ:なし
ブログ:ごめんなさい
議事録:更新済
写真:facebook済
09.10~13
「夏合宿 沖縄」
主催:ありがとう塩見
協力:サングラスのひとたち
内容:合宿、飲み会、バナナボート???
場所:沖縄のどこか
打ち上げ:???
ブログ:私は合宿行ってない
議事録:だから誰か書いて
写真:一部facebook済(残りも帰ったらあげときます)
以上です。
夏休み後半、更新サボってごめんなさい。
ずぼらで申し訳ないですが、夏休みのイベントまとめて報告します!!
畑部会や里山部会、個人活動等、私が把握していないものもあると思うので、
各自で報告よろしくお願いしますm(_ _)m
08.08
「同志社山手子供会理科教室」
主催:課外活動専門ジブリ会 森先輩と二宮
協力:同志社山手子供会のみなさま
内容:葉脈標本制作、キャンパスツアー
場所:同志社大学京田辺キャンパス
打ち上げ:なし
ブログ:更新済
議事録:更新済(参考資料として、スタッフマニュアルと企画書もあげておきました。)
写真:facebook済
08.11
「ビアガーデン」
主催:3回生
協力:2回生と1回生
内容:飲み会
場所:京都駅の某所
ブログ:自重
写真:いろいろおもしろいの撮れたけど自重
08.20
「滋賀県立大学vs同志社大学サッカー大会」
主催:高村とゆかいな仲間たち
協力:がちすか!で知り合った滋賀県立大学のみなさま
内容:サッカー大会という名の交流会
場所:同志社大学多々羅キャンパス
打ち上げ:焼肉武蔵
ブログ:二宮が怠慢ごめんなさい
議事録:更新済
写真:facebook済
08.23
「親子で環境教育」
主催:環境教育部会 吉永
協力:わがまち京たなべを美しくする会
内容:リサイクル工作、環境クイズラリー
場所:同志社大学京田辺キャンパス
打ち上げ:ルイジアナママ
ブログ:更新済
議事録:更新済(ゆきみちゃんありがとう!)
写真:facebook済
09.08
「京田辺子ども居場所作り 草木染&野菜カルタ」
主催:ジブリ会 森先輩&二宮
協力:京田辺子ども居場所作りのみなさま
内容:たまねぎを使った草木染&野菜カルタ
場所:京田辺区民館
打ち上げ:なし
ブログ:ごめんなさい
議事録:更新済
写真:facebook済
09.10~13
「夏合宿 沖縄」
主催:ありがとう塩見
協力:サングラスのひとたち
内容:合宿、飲み会、バナナボート???
場所:沖縄のどこか
打ち上げ:???
ブログ:私は合宿行ってない
議事録:だから誰か書いて
写真:一部facebook済(残りも帰ったらあげときます)
以上です。
2013年08月24日
8/23 親子で環境教育
こんにちは、二宮です!!
8/23(金)に、市役所の「わがまち京たなべを美しくする会」のみなさまと一緒に、☆親子で環境教育☆を開催しました!
まずは校内のいろいろな所に問題を隠して、大学を探検しながら、環境クイズに答えてもらう、クイズラリーをしました(`・ω・´)
みんな走り回りながら問題を探して挑戦してくれてました。
午後からは、会議室に移動して、リサイクル工作をしました!
今年は、牛乳パックを使って、びっくり箱、動物人形、招き猫の仕掛け貯金箱の中から選んで作ってもらいました。
また、みんなで牛乳パックを使ってサンバイザーを作り、それをペンで塗って、どの色が一番温まりやすく、どの色が一番温まりにくいかの実験をしました。
更に、クロマトグロフィーで、水性ペンのインクを分解する実験も行いました!
クロマトグラフィー、受け良かったです(*^^*)
今年は、3組の親子、4名の子どもに参加して頂きました。
初めは7組の親子に申し込んで頂けていたそうなのですが…ちょっと残念でしたね(^_^;)
ですが!参加した子ども達には楽しんでもらえたようですし、熱中症や怪我等もなく無事に終えられて良かったですね。
みなさんお疲れさまでした!
次回は!!
9/8(金)に、ジブリ会が、京田辺の公民館で草木染めをやります。
玉ねぎの皮を使って染めるので、野菜繋がりってことで、野菜カルタを作成途中です。
鍋が2つあるので、玉ねぎ以外の野菜でも染められないか検討中です。
何か知ってる人いたら教えてくださいヽ(・∀・)ノ
メンバーの分の布も用意できるので、みなさん草木染め&カルタをやりに来てください!
参加の連絡は二宮までヽ(´∀`)ノ
8/23(金)に、市役所の「わがまち京たなべを美しくする会」のみなさまと一緒に、☆親子で環境教育☆を開催しました!
まずは校内のいろいろな所に問題を隠して、大学を探検しながら、環境クイズに答えてもらう、クイズラリーをしました(`・ω・´)
みんな走り回りながら問題を探して挑戦してくれてました。
午後からは、会議室に移動して、リサイクル工作をしました!
今年は、牛乳パックを使って、びっくり箱、動物人形、招き猫の仕掛け貯金箱の中から選んで作ってもらいました。
また、みんなで牛乳パックを使ってサンバイザーを作り、それをペンで塗って、どの色が一番温まりやすく、どの色が一番温まりにくいかの実験をしました。
更に、クロマトグロフィーで、水性ペンのインクを分解する実験も行いました!
クロマトグラフィー、受け良かったです(*^^*)
今年は、3組の親子、4名の子どもに参加して頂きました。
初めは7組の親子に申し込んで頂けていたそうなのですが…ちょっと残念でしたね(^_^;)
ですが!参加した子ども達には楽しんでもらえたようですし、熱中症や怪我等もなく無事に終えられて良かったですね。
みなさんお疲れさまでした!
次回は!!
9/8(金)に、ジブリ会が、京田辺の公民館で草木染めをやります。
玉ねぎの皮を使って染めるので、野菜繋がりってことで、野菜カルタを作成途中です。
鍋が2つあるので、玉ねぎ以外の野菜でも染められないか検討中です。
何か知ってる人いたら教えてくださいヽ(・∀・)ノ
メンバーの分の布も用意できるので、みなさん草木染め&カルタをやりに来てください!
参加の連絡は二宮までヽ(´∀`)ノ
2013年08月19日
8/8 同志社山手子供会理科教室 反省点!!!!
二宮です。
8/8の反省文送ってくれたみなさんありがとうございました。
ようやく議事録まとめ終わりました。
遅くなってすみません(・・;)
googleドキュメントにあげておいたので、参加してくれたメンバーも、そうでないメンバーも読んでください
さて
23日にはe-cycle恒例の夏のイベント、環境教育が控えています!!
環境教育系のイベントがいろいろあってややこしいと思いますが(ややこしくさせているのは某〇ブリ会ですよね、すみません。)
23日の環境教育が正式な?本家の?なんて言うのが正しいのかわかりませんが、とりあえず代々続く伝統あるイベントです。
京田辺市と連携してイベントを開催しますよー
今年は、子供は15人ほど来る予定だそうです。
内容は違えども、共通する点も多いと思うので8/8のイベントでの反省点を挙げておきます。
8/23のイベントでスタッフをする人たち、参考にしてください!!
・大学案内での列が長すぎた。子供がいろんな方向に行ってしまって大変だった。
→後ろから見るメンバーを増やす。(メンバーの立ち位置を決める。)
→ガイドを複数にして班分けして案内する。
・謎のコーラの存在
※アクエリアスを人数分頼んだはずが、なぜか半数コーラが用意されていた。
・子供たちにしっかり話を聞いてもらえていない。
・子供たちがこの実験の目的を理解できていない。
→全員が前にいるのではなく、何人かは後ろで注意を促す。
→もう少し丁寧に説明をする。
→書き込むプリントをちゃんと説明する。時間を取らなかったのでおそらく誰も書き込んでいないと思う。家に持って帰ったところで正解がわからない。
→葉っぱを鍋で煮る理由と、鍋の中の液体の説明をする。子供たちは、なぜ鍋で葉っぱを煮るのか、鍋の中身が水なのか何なのか、理解できていないはず。
→家でも再現できるように保護者用の説明があると良い。
・キャンパスツアーの時間が押してしまった。
→高校生の時と同じように時間配分したため、小学生や幼稚園生の歩く速度を考えれていなかった。
・工作の待ち時間が長くなりすぎた。
→子供たちを前半と後半に分ける。
→作るものを何種類か用意して分ける。
→台紙のサイズが統一されてなくて、切りなおすのに時間がかかった。事前にサイズは統一して欲しかった。
→飾りを作るコーナーにかなり長い列ができていた。こだわりだしたらきりがないので、ある程度のところで妥協させるべきだった。
→全員にできないようなことは初めからしない。
→手が空いているメンバーは臨機応変に、デコレーション係や洗う係にまわるようにする。いまいち協力できていなかった。
→早く終わった子の相手をする。
→早く終わった子用に、簡単な工作的なものを用意する。
※すみません、初めはこのような案も挙がっていたのですが、私が忘れていて無意識にカットしてしまっていました。本来はクロマトグラフィー(色の分解実験)を用意しておく予定でした。他の案は、ブーメラン、浮枕子、スライムなど。
・時間内に終われず、別館管理の人に注意を受けてしまった。
→企画時間を長めに設定しておく。
→終了時間を把握していないメンバーが多かったことも原因。責任者だけでなく全員で終了時間を守れるように気を付ける。
・最後は全員で廊下までお見送りをしたほうが良い。
→時間の都合もあるが、子供には余裕を見せたかった。
こんな感じでした!!
時間内に終われず注意を受けてしまったので、今後はそんなことがないように時間厳守で!お願いします…
今回の反省を生かして、8/23も良いイベントになるように頑張りましょう^^
ではでは
明日のサッカー楽しみましょう~
8/8の反省文送ってくれたみなさんありがとうございました。
ようやく議事録まとめ終わりました。
遅くなってすみません(・・;)
googleドキュメントにあげておいたので、参加してくれたメンバーも、そうでないメンバーも読んでください
さて
23日にはe-cycle恒例の夏のイベント、環境教育が控えています!!
環境教育系のイベントがいろいろあってややこしいと思いますが(ややこしくさせているのは某〇ブリ会ですよね、すみません。)
23日の環境教育が正式な?本家の?なんて言うのが正しいのかわかりませんが、とりあえず代々続く伝統あるイベントです。
京田辺市と連携してイベントを開催しますよー
今年は、子供は15人ほど来る予定だそうです。
内容は違えども、共通する点も多いと思うので8/8のイベントでの反省点を挙げておきます。
8/23のイベントでスタッフをする人たち、参考にしてください!!
・大学案内での列が長すぎた。子供がいろんな方向に行ってしまって大変だった。
→後ろから見るメンバーを増やす。(メンバーの立ち位置を決める。)
→ガイドを複数にして班分けして案内する。
・謎のコーラの存在
※アクエリアスを人数分頼んだはずが、なぜか半数コーラが用意されていた。
・子供たちにしっかり話を聞いてもらえていない。
・子供たちがこの実験の目的を理解できていない。
→全員が前にいるのではなく、何人かは後ろで注意を促す。
→もう少し丁寧に説明をする。
→書き込むプリントをちゃんと説明する。時間を取らなかったのでおそらく誰も書き込んでいないと思う。家に持って帰ったところで正解がわからない。
→葉っぱを鍋で煮る理由と、鍋の中の液体の説明をする。子供たちは、なぜ鍋で葉っぱを煮るのか、鍋の中身が水なのか何なのか、理解できていないはず。
→家でも再現できるように保護者用の説明があると良い。
・キャンパスツアーの時間が押してしまった。
→高校生の時と同じように時間配分したため、小学生や幼稚園生の歩く速度を考えれていなかった。
・工作の待ち時間が長くなりすぎた。
→子供たちを前半と後半に分ける。
→作るものを何種類か用意して分ける。
→台紙のサイズが統一されてなくて、切りなおすのに時間がかかった。事前にサイズは統一して欲しかった。
→飾りを作るコーナーにかなり長い列ができていた。こだわりだしたらきりがないので、ある程度のところで妥協させるべきだった。
→全員にできないようなことは初めからしない。
→手が空いているメンバーは臨機応変に、デコレーション係や洗う係にまわるようにする。いまいち協力できていなかった。
→早く終わった子の相手をする。
→早く終わった子用に、簡単な工作的なものを用意する。
※すみません、初めはこのような案も挙がっていたのですが、私が忘れていて無意識にカットしてしまっていました。本来はクロマトグラフィー(色の分解実験)を用意しておく予定でした。他の案は、ブーメラン、浮枕子、スライムなど。
・時間内に終われず、別館管理の人に注意を受けてしまった。
→企画時間を長めに設定しておく。
→終了時間を把握していないメンバーが多かったことも原因。責任者だけでなく全員で終了時間を守れるように気を付ける。
・最後は全員で廊下までお見送りをしたほうが良い。
→時間の都合もあるが、子供には余裕を見せたかった。
こんな感じでした!!
時間内に終われず注意を受けてしまったので、今後はそんなことがないように時間厳守で!お願いします…
今回の反省を生かして、8/23も良いイベントになるように頑張りましょう^^
ではでは
明日のサッカー楽しみましょう~
2013年08月19日
8月19日の記事
こんちには、今日は活動日でした。
森の中はとても涼しく、クモの巣の多さと蚊に刺される事を除けば、冷房を付けているかの様な快適さです。
テストが終わり2週間が経ち、久々に山に足を運びましたが、エリア内尾根沿いのコナラ枯死個体が3本増えていました。
また木の根元には大量のフラスが溜まっており、来年度には8〜9割りのコナラが枯死すると予想を立てています。
(明確な根拠はありませんが)
今日の目的は
1、カシナガトラップの確認
2、虫取り
3、竹を使った何かを作る(個人的)
でした。
まず、1についてです。
残念な事に、2つとも失敗していました。
1つは、キャップを付けたままにしていたという初歩的な失敗、もう1つは、受け皿となるペットボトルがなくなっていた事です。
失敗の原因としましては、長期間放っておいた事でしょうか。
来年度に向けてのいい教訓となりました。
また、やっている事に関しての理解のレベルを合わせる事も大事だと思います。
次に、2についてです。
捕虫網を持っていったものの今年は樹液が少なく、昨年度のようにカブトムシが集まるといった事はありませんでした。
樹液の出る原因と雨量には何かしら関係性があるのでしょう。
最後に、3についてです。
これに関しては、ハチクを切り、節毎に切り分け、小林と二回生女子が1つずつ持って帰りました。
用途としましては、ペン立てを考えています。
森林と生活が切り離されている今において、こういう事をする意義は多いにあると思います。
メンバーが少なく少し寂しい気もします。
里山部会がいつしかにぎわうようこちらも努力ですね。
以上です。
活動時間:10:00〜12:00
活動メンバー:8人(三回生2人、二回生6人、一回生0人)
報告:小林慧人